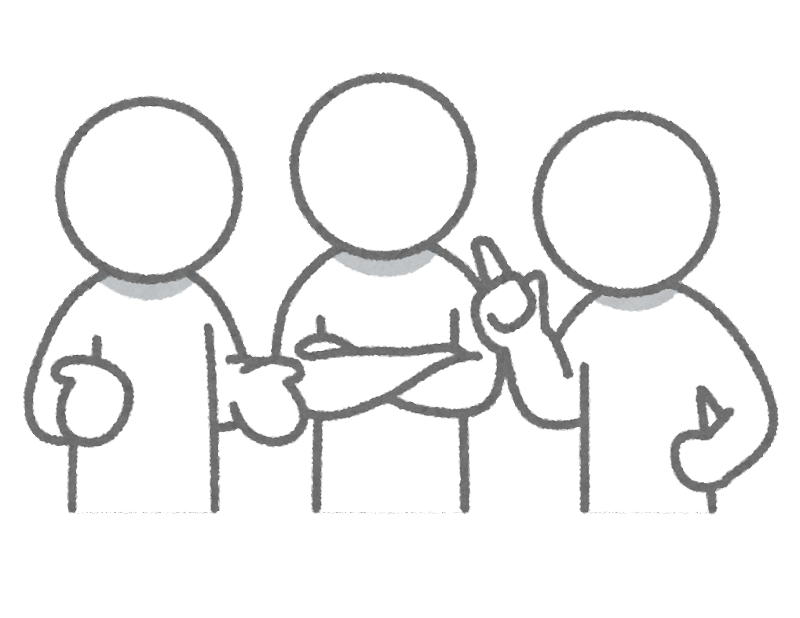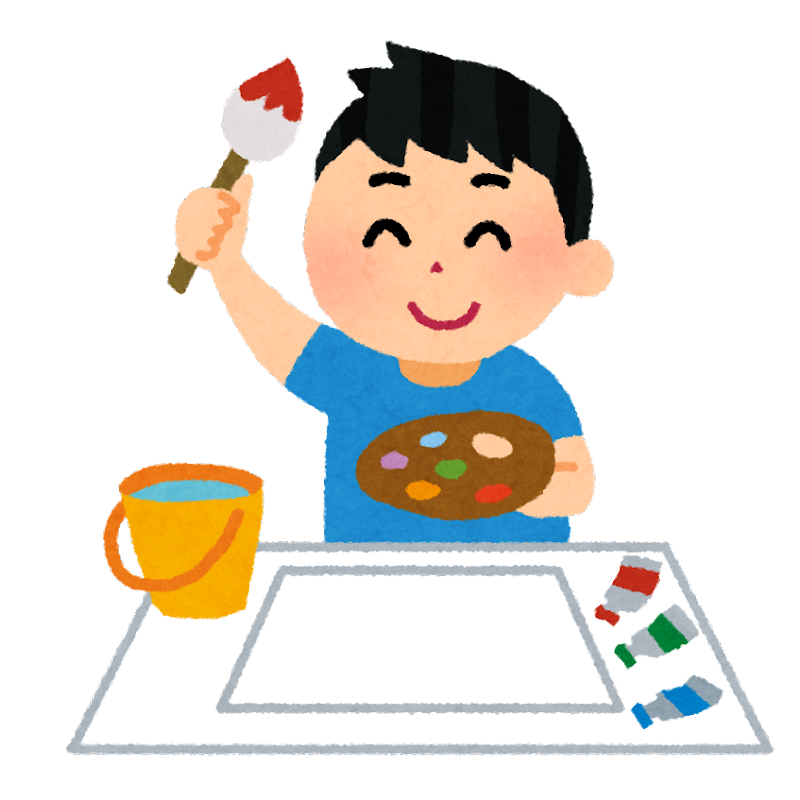今回は、私の勤う務していた学校(小学校、中学校ともに)で自校の先生方に実際に配布したものをご紹介します。これまでに、投稿した内容と一部重複するところもありますがご了承ください(一部修正しています)。
以前、ある会(校内)で「これからの教育に必要なものをボードに書ホワイトボードに書いてください」と言われました。急なことだったので慌てたのですが、咄嗟に浮かんだのが「ほんまかいなと思うこと」という回答でした。これは、今までやってきたことを一旦立ち止まって「ほんまかいな(本当にこれからもそれで良いのか?)」って見直すと意外と新しい発見があるということです。かの、「ルビンの壺」も、見えるのは本当にカップだけか?と疑う(視点を変える)からこそ、向き合う二人の顔が浮かび上がってくるのです。
こういう視点は、クリティカルシンキングと言われ、「本当にそうか?」「他にはないのか?」など、今まで持っていなかった視点で対象を見つめる視点として、PISA型「読解力」が流行った頃に特に注目されました。今まで当たり前にやってきたからそれでいい(今までと同じ視点で対象を見ることに疑いを持たない)と思うと、新しいアイデアが出てこないばかりでなく、今までやってきた本質的な意義すら見落としてしまうことになりかねません。
また、クリティカルは「批判的」と訳されることが多いのですが、これは若干誤解を生みやすい。正確に言うと単なる批判ではなく「建設的な批判」という意味であり、どちらかというと「吟味」のほうが意味としてはしっくりきます。目の前の対象が本当に必要なのかどうか、改革できる部分はないかと「吟味」するために、これでいいのかという目で見てみましょうということです。
その視点を持つためには、自分の価値観を一旦保留する必要があります。これを現象学ではエポケー(判断停止、判断保留)と言います。
例えば、インドの人はカレーを手で食べることがありますが、これを日本人がはじめて見れば、違和感を持つ人もいるでしょう。それは、日本で生まれ育ってきた者には、素手でごはん食べるという習慣がなく、むしろ行儀が悪い「良くない」こととして周囲の大人から躾けられてきたからです。でも、手でご飯を食べているインドの人に向かって「なんという非常識な」と思ってしまったら、インドの文化やそこに生きてきた人々を理解することはできません。私たちは、日本の常識や文化は一旦保留して、そこにどんな意味が込められているかを考えてこそ相手を理解することができるのです。
また、「江戸時代は強固な身分制のため職業選択の自由がなくて、当時の人は不幸だった」という命題に対してそれが本当かどうかを確かめようとするとき、現代に生きる者は、まず「自由は人間の不可侵権利だ」という価値を一旦保留(判断停止)する必要があります。そうしないと、「そんなもの不幸に決まっている」と決めつけてしまう恐れがあります。でも、当時の人たちに「自由=不可侵の権利」という視点がそもそもなかったとしたら、あるいは職業は選べるものだという選択肢すら頭になかったとしたらどうでしょう。おそらく、魚屋の子は小さい頃から魚屋である親の姿を見て育ち、自分が跡を継ぐつもりで仕事を覚えていったでしょう。そして、少しずつ自分でもできることが増えていくことに喜びを感じていたことは容易に想像できます。かつて、エイリッヒ・フロム(ドイツの社会心理学者)が、自著『自由からの逃走』で「人は自由が多すぎると逆に束縛を求める存在だ」と指摘した通り、選べないからこそ迷うことがなく、多様な自由が保障される現代より幸せだったかもしれないのです。
私たちは、日々生徒やその保護者に接していますが、その言動がどうにも理解できないと思うときがよくあります。そんなとき、インドの人を理解するときと同じように、江戸時代の人々の願いに思いを馳せるときと同じように、一旦、学校の常識や教育の「当たり前」を封印する必要があると思います。私たちは、ついついこれまでの指導観や人物観を強く持ちすぎて、偏見や臆見、憶測を十分に捨て切れなくなることがあります。相手や対象物を「色眼鏡」でみてしまうことがないかどうか、常に振り返る必要があると思うのです。
学校教育の例も一つ挙げておこうと思います。「不登校」についてです。不登校はかつて登校拒否と呼ばれていました。日本における登校拒否の研究は、アメリカの「学校恐怖症」の研究を基礎として始まっており、学校に来られないのは何かしらの(心理的な)病気であるとして、子どもや保護者に対するケアが行われました。その実績は教育界に大きな影響を与え、多くの苦しむ子どもたちやその保護者を救ってきました。
それに対して「ほんまかいな」と異を唱えたのが、当時大阪市立大学の助教授だった森田洋司氏です。森田氏は自著『「不登校」現象の社会学』(学文社1991)の中で、不登校(当時は登校拒否)を社会的な現象として捉え、できるだけありのままに分析し、子どもが学校に来られなくなる原因は、必ずしも個人的な要因にとどまるものではなく、社会的な価値観の変化が大きく影響していることを明らかにしました。組織や会社などを公的なものと捉えていた価値観が相対化され、個人の幸福を優先する現象(私事化)が社会全体に広がっている。その相対化は当然学校にも向けられ、学校は何を置いても登校すべものだという考えが薄まってきた。そのため、子どもや親は学校を「行くか、行かないか」といった選択可能なものとして捉え始めているというわけです。これは、学校関係者に少なからず衝撃を与えました。森田氏は、私たち学校に警告を発したのかもしれません。つまり、子どもたちが登校する必然性を創造する(子どもにとって楽しい学校、行きたいと思える学校など)努力によってつなぎ止める工夫をしなければ不登校現象はさらに深刻になると。その後「不登校」は、全国的に急速に広がり、森田氏の指摘は残念ながら的中していると言わざるを得ません。
森田氏の研究は、「どうして、ほとんどの子どもたちは学校に来ることができているんだろう」という視点から始まりました。それまでの研究は「どうしてこの子は学校に来られないのか」という視点から為されていましたから、まさに、真逆の視点です。登校拒否を個人の問題として捉えていれば決して生まれなかった発想です。その後、森田氏はいじめ問題の研究にも取り組み、「いじめる側」と「いじめられる側」という対立構造で語られることが多かった問題に、「観衆」や「傍観者」という新たな視点を入れて、いじめを支える四層構造を解明しました。今では、いじめ問題を考えるときの常識になっています。これもそれまでの常識を一旦外し「ほんまかいな」という視点を現状に向けることで真実をあぶり出したのです。
こうした考え方は、様々な学問領域で用いられています。社会学、現象学、現象学的社会学などの世界ではもうずっと前から言われてきたことなのです。でも、これまで教育についてこれらの学問があまり深く関わってくることはありませんでした。つまり、研究対象として学校を扱うことが少なかったということです。それは、教育学の内容が多くの国民や教員の納得のいくものであって、疑いようのないものだったからであり、社会全体でその価値を支えていたからだと思います(学校のことは先生に任せておけばいいという時代)。誰もが当たり前だと信じる強固な価値観は、強固であるが故に誰もそれを疑うことなく「ほんまかいな」という視点を持つこともなかったのだと思います。
これまで日本には疑う余地のない「勤勉」という価値がありました(今でも多くの人が肯定するでしょうし、私もこの価値を否定するつもりはありません)。しかし、社会は変化し、終身雇用制が揺らぎ始め、「24時間働けますか」と言われながら、毎日毎日残業で家庭も顧みず、全てをかけて会社のために働いてきた人たちが次々にリストラの憂き目に遭う、なんともやりきれない現象が起き始めます。こうなると次の世代の若者が、同じようになりたくないと考えるのは無理のないことです。そして、人々にとって「勤勉」という価値は、次第に絶対的なものから相対的なものへと移行し始めます。つまり、私事(ワタクシゴト)を重視する人が増えていったのです。かつて、デートを理由に残業を断る若者が「責任感がない」とか、今さえよければいいとする「快楽主義」だとして非難されたことを覚えている人もいるでしょう。それは、若者のそうした姿が、大人にとっては解消しなければ(なくさなければ)ならない「問題」として映ったからでしょう。これは、「まじめ」や「勤勉」が崩壊していくことに強い危機感を抱いた大人たちが、徹底してこれまでの価値観を守ろうとした現象であるとも言えます。
しかし、若者は本当に間違っていたのでしょうか。相対化がもたらした社会の「私事化」は、見る角度を変えれば、人として豊かな生き方って何だろう(会社人として生涯を終えることが幸せなのか)、ちょっと立ち止まって考えてみようという人が増えた証拠でもあります。思えば私たち教師も、長年に渡って子どもたちに、お金や地位だけが全てじゃない、人として豊かな人生を送ってほしいと願ってきました。相対化現象が広がる中で、皮肉にも私たち教師の教えを若者が体現したのかもしれません。
社会がどんなに変わっても子どもの本質は変わらないと言う人がいます。その人たちが言うように、インターネットやSNSなどの情報機器がどんなに発達しようが、AIがどんなに進化しようが、人が大切にしなければならないことは変わらないのかもしれません。でも、かつてグーテンブルグが活版印刷を考案した(諸説有りますが)とき、世界の価値観は本当に変わらなかったと言い切れるでしょうか。ベルが電話を発明したときはどうだったでしょうか。恐らく、それまで信じられなかったようなことが当たり前になり、それによって人の考え方や価値観も大きく影響されたと思います。何が起こっても子どもは変わらない。だから、教育も変える必要はない。これは、教育に携わる者の「傲慢」かもしれません。少なくとも、私たちはプロとして「本当に今のままでいいのか」という自省は重ねていかなければならないと思います。
参考:とんでもない「ほんまかいな」を一つ紹介。1960年、フランスの歴史学者フィリップ・アリエスという人が『<子供>の誕生』という本を刊行し、子供と大人の一線を当然視し、学校教育制度を当然視する現代の子供観に対して疑義を呈しました(「ほんまかいな」の視点です)。アリエスは、中世ヨーロッパには教育という概念も、子供時代という概念もなく、 7〜8歳になれば、徒弟修業に出され大人と同等に扱われ、飲酒も恋愛も自由とされたと述べています。つまり、ヨーロッパにおいて子供という概念はもともとあったものではなく、学校教育制度が生み出したものであることを示したのです。
「人は変わり続けるからこそ、変わらずにいられる」
これは、カナダ出身のシンガーソングライター、ニール・ヤングさんの言葉で、松任谷由美さんもコンサートなどでよく使われるそうです。まさに、これからの教育にぴったりの言葉だと思います。教師個人としても、一人の人間としても、学校全体としても、あるいは日本全体の教育としてもこの視点はとても大切になってくると思います。
私は、どんなに時代が変わろうと教育(学校ではありません)の神髄は同じだと思います。これだけ「ほんまかいな」の視点が大切だと力説していたくせに、矛盾しているじゃないかと思われるかもしれません。そうではなく、本当に大切なもの、変わらない教育の神髄を守るためにも、私たちは変化に敏感である必要があるのです。今までの価値観で新しいものを否定することで、逆に一番大切なものも失う可能性があるのです。
今、私たちには、教育の本質を見極めるために自分たちのやってきたことをしっかりと吟味することが求められています。エポケーという概念も、ニール・ヤングさんの言葉も、今まで気づかなかった真実の在処をきっと教えてくれると私は信じています。本当に大切なものは子どもたちが安心して成長できる環境を整えることから始まるのだと思います。(作品No.94HB)