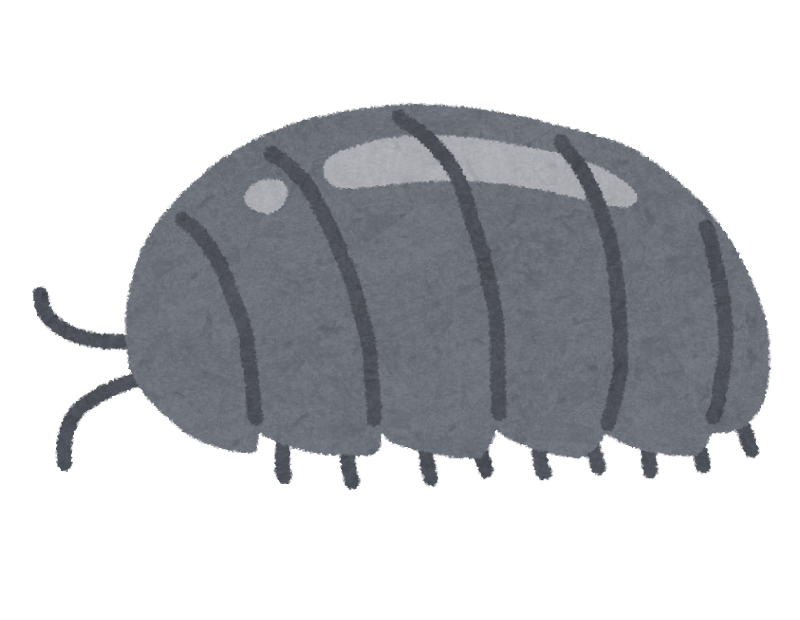教諭時代、16年間野球部の顧問をさせていただきました。私は、中学時代は野球部でしたが控えでしたし、高校の野球部は故障が原因で中途退部しました。大学ではソフトボール部で、チームは毎年のようにインカレに出場していましたが、レギュラーには結局なれませんでした。もちろん野球の指導については素人ですし、実績(戦果)にも目立ったものはありません。わずかにあるとすれば、10年連続で一つ上の大会に駒を進めたくらいのことくらいです。でも、一つだけ自分の中で誇りにしていることがあります。それは、姑息な手段を使うことや、相手チームの選手を危険にさらすようなラフプレーだけは絶対にさせなかったことです。
顧問時代、勝つためなら手段を選ばないチームにたくさん出会いました。例えば、ホームでのクロスプレーの際、スライディングをする走者が捕手のミットの先端を狙ってスパイクを立ててくるチームがありました。ミットの端にスパイクを当てて捕手のミットからボールをこぼさせようとするわけです。練習試合ということもあり、私は特に抗議はしませんでした。でも、試合後部員を集めて言いました。「ああいうプレーを高等な技術だと思うようなチームには絶対にしたくない。あのスライディングは一つ間違えば捕手の顔面や手首にスパイクの刃が当たって大けがとなる。何より、たとえ敵であっても同じ野球をする仲間だ。自分のことしか考えない野球がしたいと思うのなら他のチームでやってくれ。」と。
他にも、いわゆるクイックピッチを繰り返す投手にも出会いました。監督の指示です。クイックピッチとは打者が構えるのを待たずに、捕手からの返球を受け取ってすぐに投球することで、打者はタイミングを合わせることができません。ルール上もボーク(危険球の一種)扱いとなります。ただ、クイックピッチの判断は微妙なところがあります。ボークになるかどうかのギリギリのタイミングで投げさせているのです。それでも野球の理念に反することは確かです。その理念とは、正々堂々と戦うこと、相手をだますプレーはしないことです。クイックピッチは打者の不意を突くことであり、正々堂々を旨とする野球の理念に反します。また、ベンチのサインを窺っている打者に投球が当たると非常に危険です。通常の死球なら、当たりそうな投球に対して打者は一瞬体に力が入り、万一当たっても被害が最小限にとどめることができます。しかし、不意を突かれての死球は体に緊張感がないため、大けがにつながりやすいのです。投手が牽制球をする際、必ず軸足でない方の足をまっすぐ投げる塁に向けて踏み出すことがルール上義務付けられているのも、同様の理念に基づくものです。それは、走者に対して牽制球を予告するという意味があり、打者に投げるふりをして突然牽制球を投げるのは走者をだますことになるからです。こうした理念によって野球は紳士的なスポーツとして成立しているのです。

私は、相手の顧問に「あれは、クイックピッチじゃないですか?」と指摘しました。しかし、その顧問は「地区の大会でも何も言われていない」と聞く耳を持ちませんでした。
さて、先述のクイックピッチを続けた投手は、どんな気持ちでマウンドに立っていたのでしょうか。指示した監督はいったい野球を通じて何を伝えようとしていたのでしょうか。生徒が「嫌だけど監督が言うから仕方がない」と思っていたのならまだ救われます。でも、その子が「これはいい方法だ」と勘違いしていたとしたら、人をだますことを覚えるために野球をやっているようなものです。
野球は、実によくできた競技です。どんなにすごい投手であっても、稀代のホームランバッターであっても決して一人では勝てません。また、それぞれの個性に合わせた出番が用意できます。仮にチームで一番足が遅くても、バッティングがよければ代打で出場できます。逆に守備も苦手、打つのも苦手だけど、足が速ければ代走で出場可能です。状況判断に長けた者は三塁のランナーコーチで活躍できます。少しでも野球を知っている人なら、三塁のランナーコーチがどれだけ重要なポジションかおわかりだと思います。
他にも、相手投手の気持ちを考えて打席に立つことも求められますし、的確な状況判断も必要です。仲間のミスを最小限にするため、野手は一球一球、打球や送球のカバーに走ります。人として学ぶべき要素がふんだんに含まれています。野球は人生の縮図だと思います。
「甲子園に行けるチームと行けないチームがあります。行けないチームには野球以外の部分で何か足りない部分があるのだと思っています。そういうことを野球の神様は見逃してくれないんです」
阪神・淡路大震災直後の1995年にセンバツ大会でベスト8進出を果たし、地元神戸に勇気を与え、チームを通算8回も甲子園に導いた神港学園の前監督北原光広氏から直接伺った言葉です。
今、部活動が地域に移行されようとしています。全国的に教職希望者が激減している状況では、教員の業務改善を実現するためにも避けられないでしょう。でも、どんな形で移行されるにしても、これまで学校部活動で大切に積み上げてきた「子どもの成長」を支援する姿勢だけは確実に受け継ぐものであってほしいと心から願います。(作品No.157RB)