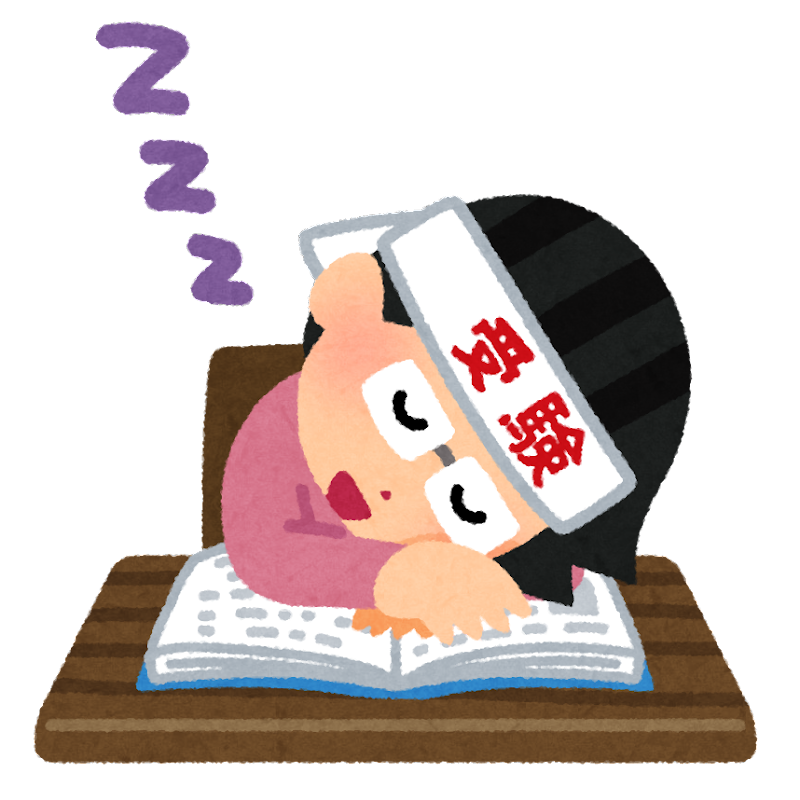以前から、生徒指導は「生徒理解に始まり生徒理解に終わる」と言われ、子どもの言動や振る舞いを細かく観察するのはもちろん、家庭環境、成育歴などできるだけ多くのことを情報として知っておくことが大切であるとされてきました。今でも、その基本は変わっていないと思います。
1981年(昭和40年)に当時の文部省が示した『生徒指導の手引き』では、生徒理解の対象を「能力」「性格」「興味」「要求」「悩み」「交友関係」「環境条件」など、かなり広い範囲に求めています。また、2010年(平成22年文部科学省)の『生徒指導提要』にも、次のような記述があります。
「児童生徒を多面的・総合的に理解していくことが重要であり、学級担任・ホームルーム担任の日ごろの人間的な触れ合いに基づくきめ細かい観察や面接などに加えて、学年の教員、教科担任、部活動等の顧問などによるものを含めて、広い視野から児童生徒理解を行うことが大切です」(p.2)

でも、いずれの記述も「生徒理解とは何か」について、直接説明しているわけではありません。いくら「多面的」「総合的」に「広い視野」から理解せよと言われても、私たちは児童生徒のすべてを理解することはできません。なぜなら、人は日々変化するものだからです。変化を続けるものを完全に理解することは理論上不可能です。それを「いつか、すべてを理解することができはずだ」と考えてしまうと、教師は何かあったときに「もっと理解できていれば」と悔やむことになります。
結論を言えば、「生徒理解」とは、児童生徒によって「この先生は、自分のことをわかってくれている」と感じる瞬間のことをいうのだと私は思っています。いや、それは方向が違うだろうと思われるかもしれません。でも、そう感じるのは私たちが「教師が生徒を理解する」という意識が強いからだと思います。
教師がいくら児童生徒のことを十分に理解していると思っていても、子どもの方が「もっとわかってほしいことがある」と思っていれば理解したとは言えないでしょう。そもそも人が人を「完全に」理解するということ自体が不可能なのですから、大切なのは、一から十まで理解することではなく、まずは「私はあなたを理解しようとしていますよ」というメッセージを児童生徒に届けることです。
そのメッセージを伝えるためには「相互作用」が必要です。多くの会話を交わし、一緒に作業するなどして、互いが互いをわかろうとし合える関係をつくることです。例えば、教師がAさんに言葉をかければ、その言葉によってAさんの物の見方や考え方に影響を与えます。つまり、厳密に言えば、Aさんは教師の言葉かけによって微妙に変化しているのです。その変化したAさんが、今度は教師に何かしらの反応を返します。それを受けて教師はAさんの新しい面を見つけます。そのとき、教師の方もAさんに対するイメージに微妙な変化が生まれます。これが「相互作用」であり、その繰り返しによってAさんは「先生は自分のことをわかろうとしてくれている」と感じるようになります。そして、最終的に「わかってくれる」という信頼関係につながります。
成育歴や家庭環境、交友関係を知ることはこうした「相互作用」が、より自然に進めるために重要なのです。
抽象的な書き方になりましたが、結局「児童生徒理解」とは、相互に分かり合おうとする関係のことをいうのだと思います。教師が教師の判断で「この子はこういう子だ」と結論づけた時点で「相互作用」は停止し、子どもはどんどんわからない存在になっていきます。
(作品No.96AB)