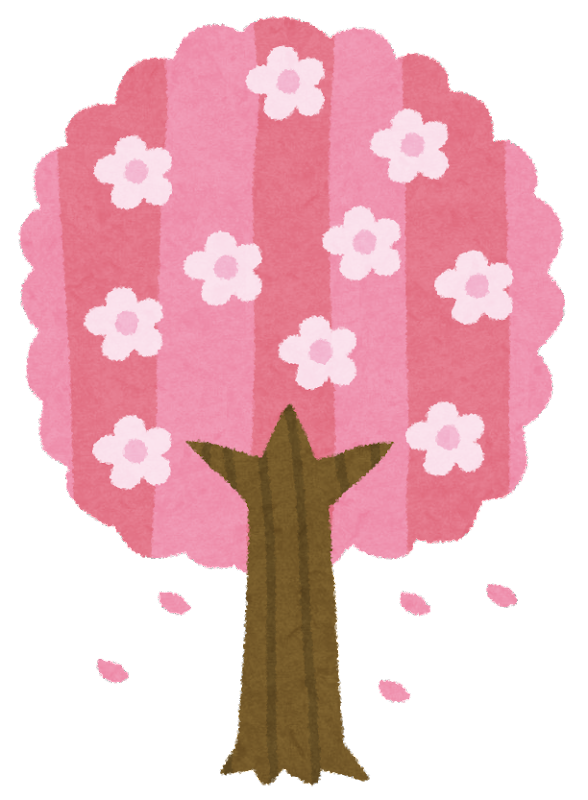最近、ペット型ロボットが流行っているそうです。近年のロボットはかなり精巧につくられていて、本物と遜色のないものも増えているようです。まあ、それでも大人ならロボットが生き物ではないことに気づくでしょう。たとえ、見た瞬間は生き物に見えても、ちょっと落ち着いて見れば見分けがつくはずです。
でも、子どもならどうでしょうか。それも、就学前の幼児の場合、同じように識別できているのでしょうか。幼い子どもは、大人に比べて知識も経験も少ないので、もしかしたら精巧につくられたペット型ロボットを「生き物」と勘違いすることもあるかもしれません。
この点について、ある人が面白い研究結果を発表しています。その人によれば、幼稚園に動物の形をした動くロボットを置いておくと、しばらくは何かを食べさせたり、話しかけたりするなど「生き物」として認識している行動を示しました。しかし、2週間くらいたつと誰も「世話」をしなくなりました。そこで、幼稚園の先生が「かわいそうだね。世話をしてやろうよ」と促しますが、それでもまったく興味を示さなくなりました。つまり、最初は動くロボットを生き物だと認識していた子どもはロボットを命を持たない「無機物」であることに気づき、おもちゃに飽きたときと同様、振り向きもしなくなったというのです。
この実験に参加した幼稚園ではうさぎを飼っていたそうですが、子どもたちはうさぎの世話はずっと続けているそうですから、子どもたちは命あるものとそうでないものを(2週間はかかったものの)しっかりと区別することができたということになります。
さて、この実験研究で興味深いのは、論文のまとめの部分で、子どもたちがロボットと生きたうさぎを区別する基準が「弱さ」だったのではないかという推論で締めくくられていることです。飼われたうさぎは誰かが餌を与えなければ生きていけません。子どもはうさぎの世話をすることで経験的にそのことを知っています。ところが、ロボットは世話をしなくても、ずっと同じ動きをします。自分の世話を必要としないロボットは、子どもにとってもかけがえのないものとはなりません。「弱さ」は、生き物を認識する重要な要素であり、生きていくためには何らかの世話や支えが必要であるという意味で、生きとし生けるものに共通している要素なのです。
アメリカの哲学者ミルトン・メイヤロフは「他の人々をケアすることをとおして、他の人々に役立つことによって、その人は自身の生の真の意味を生きているのである。」1)と言っています。メイヤロフは「ケア」の対象を人間だけに限定せず、他の生き物はもちろん、概念や事物にまで視野に入れていました。子どもが無心に小動物の世話をする(役に立つ)ことは、自分の存在が小動物にとってかけがえのないものであると感じることでもあります。その感覚によって、こどもは自分自身の存在価値を自覚することができます。
子どもに限らず「ケア」する対象を持つことは相手の「弱さ」を受け入れることであり、同時に「ケア」する側にも自分の生きる意味を与えてくれることなのです。
自分にとってかけがえのない誰か(何か)がいるということ、それこそが生きる居場所であり、自尊感情の源だということを純粋な子どもは本能的に知っているのかもしれません。
1) ミルトン・メイヤロフ著、田村真・向野宣之訳(1987)『ケアの本質』(ゆみる出版)、p15
参考文献:坂田陽子(2020)「ペット型ロボットの疑似飼育は子どもの生物概念を発達させるか」、『発達心理学研究 第31巻 第4号』 183-189
(作品No.213RB)