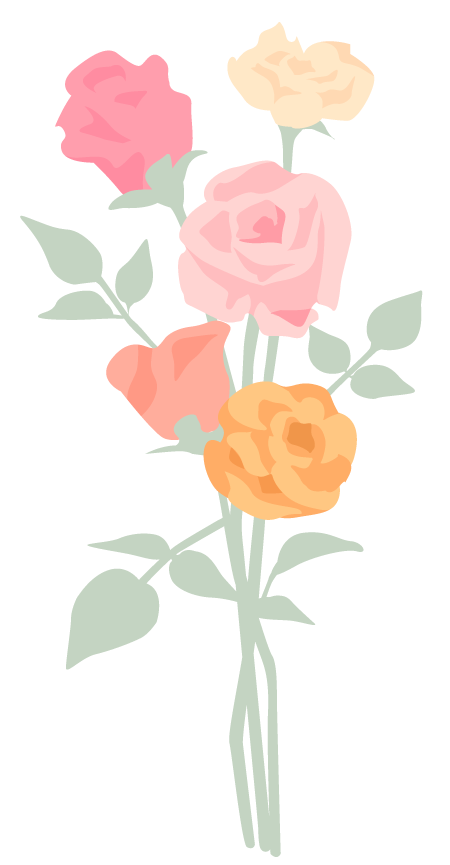教員にとって、子どもをどう褒めて、どう叱るかは永遠の課題だと言われ、古くて新しい問題です。
中学校の教諭時代、私のクラスにMさん(2年生男子)という子がいました。口数は少ない子でしたが、非常にまじめな子でした。特に、掃除の時間では、周りの子がどんなにサボっていても、いつも黙々と掃除に取り組んでいました。
ある日、私は教室の真ん中で、周囲に聞こえるようにMさんを褒めました。
「Mさんは、いつ見ても手を抜かずにがんばってるなあ」と。
その瞬間、信じられないことが起こったのです。普段温厚で怒りをあらわにすることなどまずなかったMさんが、突然、ほうきをその場に投げ捨て、教室の隅で座り込んでしまったのです。その顔には「怒り」ともとれる表情が伺えます。状況から考えて、私が褒めたことが原因だというのは理解できましたが、それでもなぜこうなったのか、若かった私にはまったくわかりませんでした。

その日の放課後、家庭訪問をしてMさんのお母さんと話をしました。そのとき初めてMさんの気持ちがわかりました。お母さん曰く、
「あの子は、ものすごくまっすぐな性格でね。もうちょっと融通がきく子になってほしいと親の私でさえ思うことがよくあるんです。今日、帰ってきて話してました。自分はやるべきことをやっていただけなのに、あんな褒められ方をしたら、褒められるためにやっていることになってしまうって。そういう子なんです。」
子どもは褒められて喜ばないはずはないという私の思い込みが、Mさんの誇りを傷つけてしまったのです。
私たちは、子どもが何かよいことをしたら褒め、良くないことをしたら叱ります。それはそうした評価を積み重ねることによって子どもに少しでも正しい行動がとれるようにという教員の願いでもあります。そして、基本的には叱るより褒めることの方が大切だと思っています。でも、褒められる側に立った褒め方でなければ、私のような失敗をしてしまうことになります。小学校の低学年なら、ほとんどの子はみんなの前で褒めてやれば喜びますが、思春期真っ只中の子に同じように褒めても効果があるとは限りません。
冒頭のMさんのケースで言えば、失敗の最大の原因は、私に「邪(よこしま)な」考えがあったからです。私は、Mさんを利用して、他の子に「真面目に掃除しろ」というメッセージを送ろうとしたのです。これでは、本当に褒めたことにはなりません。私の邪な考えをMさんは即座に見抜いたのです。
子どもを褒めるときに大切なのは、その子が今何を考えているのか、どういう個性を持っているのかを踏まえておくことだと思います。当然、発達段階も視野に入れなければなりません。そして、発達段階は単純に年齢で決まるものではありません。そうしたことが頭にあれば、私の失敗は防げたと思います。Mさんのような子には、掃除時間以外にさりげなくMさんにだけ伝えるべきだったのです。
さて、ここで「褒める」」についてもう少し深く考えてみようと思います。
アドラーによれば、
「「ほめる」のは、相手が自分の期待していることを達成したときです。言ってみれば条件つきののごほうび。逆に期待に応えられないと、ほめるどころか失望を表現されて勇気がくじかれる可能性もあります。」1)
となります。
褒めることが「条件つきのごほうび」だとすると、私たちが考えなければならないのは、その「条件」が子どもにとって本当に価値のあることかどうかということです。私たちは得てして深く考えずに「これは良いことに決まっている」という常識にとらわれがちですが、これだけ社会全体に多様化が進んでいることを考えれば、いつまでも同じ価値が通用するかどうかはわかりません。また、私たちが正しいと考える価値は生きていても、そこから派生するさまざまな考え方が生まれていてもおかしくはありません。私たちは、社会の価値観の変化に積極的に目を向けなければならないと思います。
また、アドラーは
「人と比べて「ほめる」と、必要以上に他人との競争を気にするようになります。」2)
とも言っています。冒頭の私の失敗の原因は、まさにここにあります。
最終的にアドラーが大切にしたのは、「褒める」よりも「勇気づける」ことです。
「勇気づける」とは、あくまでも言葉を受ける側の立場に立って、その人の行為そのものを認めることで、その人の意欲を引き出そうとするものです。決して、結果だけを「褒める」のではありません。
例えば、テストで100点を取った子に「よく頑張ったね」と褒めたり、何かの大会で優勝した子を「すごい」と称えたりしますが、こういう数値や客観的な結果で表すことができるものは、簡単に他と比較できてしまいます。褒める側にその気がなくても受け止める側からすると、今後も他者と比較することで承認欲求を得ようとしてしまいます。
100点を取って、褒めてもらおうと先生のところに飛んできた子には、100点を褒めるのではなく「あなたは、授業中にいつもしっかり話を聞いていたよね。それが素晴らしいんですよ」と、行為を確認することが大切だということです。そして、そういう認め方をするためには、普段から子どもの様子をしっかり見ていることが必要になります。
行為を認めるということは、その子をまるごと承認するということです。だから、自尊感情は継続するとアドラーは言います。
東京都の私立中高一貫校、栄光学園の数学教員である井本陽久氏は、長い教員生活で紆余曲折した結果、ある時期から「子どもを叱らない」と決めたそうです。その代わりに子どもの存在を丸ごと受け入れようと決意して、今やカリスマ教師とまでいわれるようになりました。
栄光学園は、毎年東大合格者数がベスト10に入るほどの進学校ですが、井本氏は栄光学園だけでなく国内外の児童養護施設でも成果を挙げています。決して、学力の高い子や環境的に恵まれたこだけと関わっているわけではないのです。
私は、カリスマといわれる教員と同じようにしなければいけないとは考えません。そもそも、その人が本当にカリスマだとしたら、滅多にいないからこそカリスマなわけで、だれでもすぐに真似できるようなレベルならだれもカリスマとは呼ばないでしょう。また、中途半端なカリスマ(実際一部の人からしか認められていないカリスマも存在します)はかえって他の教員がやりにくくなることもあります。
でも、子どもを叱らなくても学力をつけることに成功している人がいることもまた事実です。井本氏の授業では全員が自ら進んで学習に取り組んでいると言います。
おそらく井本氏の子どもへの関わり方は「褒める」から「勇気づけ」に進化した結果生まれたものではないかと思います。
そのまま真似をする必要はないと思いますが、「勇気づけ」というキーワードを頭にいれておくだけで、子どもたちはきっと、いきいきとした表情を見せてくれるようになるでしょう。
そうなれば、教員の暴言や、不適切なかかわりなどとはまったく無縁の空間が、そこには広がっていくと思うのです。
1)永藤かおる著・岩井俊憲監修(2017)『図解 勇気の心理学 アドラー超入門』(ディ スカバー・トゥエンティワン、p36、中段)
2)前掲書、p36、下段
(作品No.185RB)