野球部の顧問になって5年目くらいのころ(今から30年近く前)からだったと思いますが、部活動結成会で野球部通信を生徒に配り、そこに必ず「特別になるな」という見出しで次のように書くようになりました。

「野球はとても注目度が高いスポーツだ。地域の小さな大会でさえチーム紹介や試合結果が掲載される。時には写真まで。だからときどき「野球をやっている自分は特別だ」と勘違いする者が出てくる。野球のためだと言えば何でも許されると思ってしまう。そういう者は、自分がやりたいことや好きなことには熱心だが、必要なことでも、嫌いなことには手を抜く。そうした自分中心な考え方は必ず雑なプレーを生む。また、人のミスを許すことができず、自分のミスには言い訳をする。そして、チームの雰囲気を悪くし、新たなミスを生み出す。そして、互いに信頼できなくなって大敗の原因となる。
君たちは、何も特別な存在ではない。それは、たとえば君たちの中に将来プロ野球で活躍できるほどの素質を持っている者がいたとしても同じことだ。君たちは野球が好きで野球部に入ってきた、普通の中学生である。つまり、野球部員である前に本校の生徒である。だから、学校のルールを守るのは当たり前のことだ。安易に学校のルールを破る者は、野球もぞんざいに取り組むと私は判断する。そんな選手と一緒に野球がしたいとは思わない。」
この野球部通信は、当時、近隣地区においてその安定したチーム力で定評のあったA中学校野球部顧問のK先生の通信を参考にしたものです。とにかく何回やっても勝てなかった相手でした。あるとき、K先生にチームづくりのポイントを尋ねたら、ご自身が出しておられた野球部通信を何部かくださったのです。
驚いたのは、そこには、A中野球部の方針として,「練習試合を除き、練習は2時間を越えない。」と書かれていたことです。もちろん土日も同じ基準です。長い練習は集中力を低下させる。「今日は練習が長い」と思うと、子どもたちは力を温存するために無意識に練習前半で力を抜くようになる。逆に時間を短縮すると、できるだけ効率の良い練習をしようとして工夫や努力が生まれる、それがK先生の持論でした。
ある年の春、一度練習の様子を見せていただいたのですが、私にとっては何もかもが新鮮でした。K先生の練習メニューには「打撃練習」とか「守備練習」といったカテゴリーが存在していないのです。つまり、ほとんどのメニューに複数の要素が盛り込まれているため、これは打撃練習だと定義することができないのです。トスバッティングには守備の基礎練習や送球練習が組み込まれているし、バント練習には体力強化ダッシュが入ります。フリーバッティングでは、必ず走者がつけられてゲージの打者に合わせてスタートを切る練習をしています。時にはアウトカウントやイニングを設定することもありました。要素が増えれば、当然一人一人の動きは多くなります。そうなると気を抜く暇はなくなります。部員は常に動いている状態となり、30分もすれば部員たちはみんな息が上がりそうになる。結果、体力、集中力共に飛躍的に向上したといいます。
また、メニューはすべて実戦に結びついていました。たとえば、ベースランニングでは、必ず場面設定(アウトカウントや得点差、イニング、打球の方向など)がなされ、打球がどこに飛んだかを含めて次の走者が状況を指示します。前の者と同じ設定は御法度。緊張感が持続しているのがわかります。体だけでなく頭もフル回転です。でも、生徒たちは実に楽しそうでした。悲壮感などかけらもないのです。
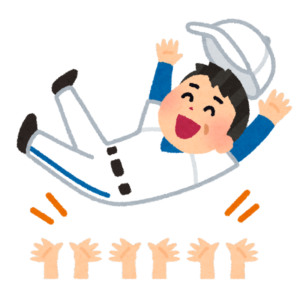
その年(平成2年)の夏、K先生率いるA中学校は当地区初の全国大会出場を決め、ベスト4まで駒を進めました。私は、全国大会に出ることや、そこで勝ち進めたことにのみ価値があるとは決して思いません。実際そのときチームには、詰まった当たりのショートゴロで二塁から余裕でホームインするほどの俊足の子や、かすりもしないスピードボールを投げるエースもいました。明らかに運動能力の高い選手が揃っていたのです。「どこまで勝てるか」は「どんな選手がいるか」によっても大きく左右されます。
しかし、K先生の次の言葉を聞いたとき、私は目の前の勝利を遥かに超越した中学校野球の神髄を感じました。そしてその精神は、部活動が中学校から地域主導へと移りゆく今だからこそ、子どもたちの持つ可能性を最大限に引き出すために受け継がれるべきものだと思います。
「私がこだわってきたことは二つだけです。一つは部員が辞めない部にすること。もう一つは、控えの選手や入部したばかりの1年生が生き生きと活動できること。それだけです。」
(作品No.1H-2)


