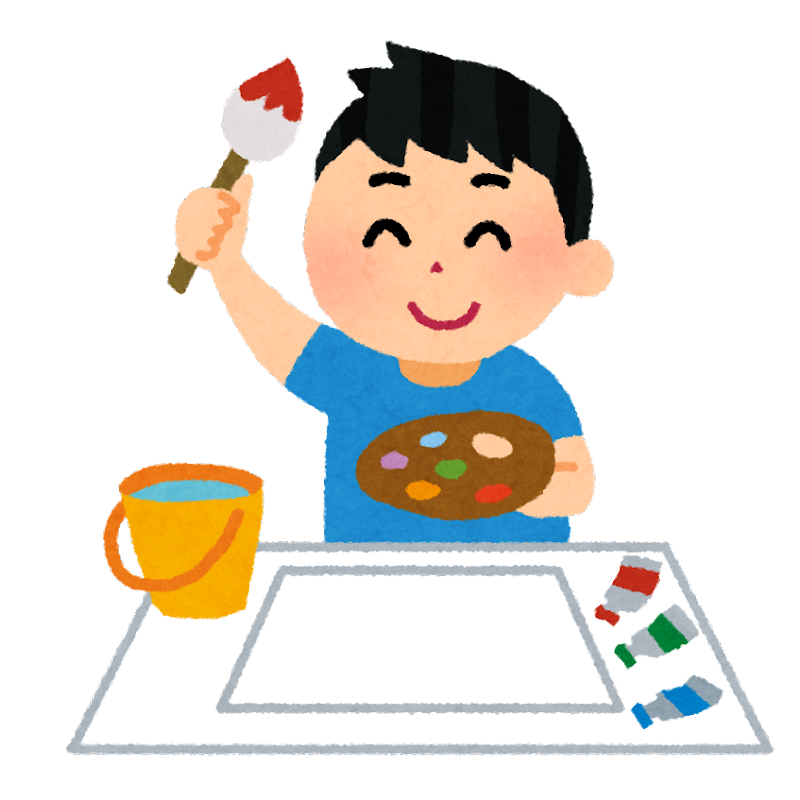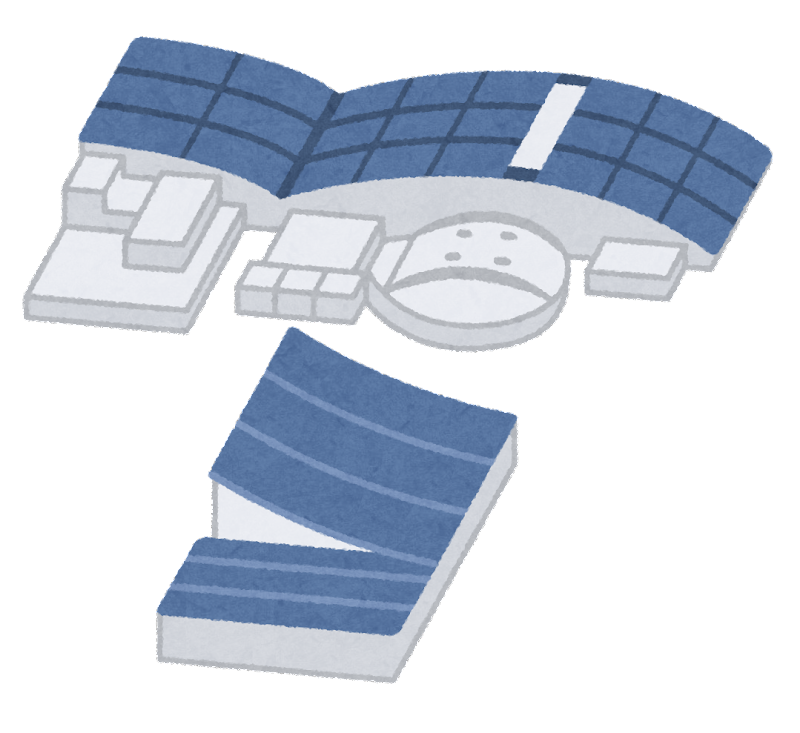最近、小中学校のPTAに対する「異議申し立て」が多くなっています。都道府県の中には、全国組織である日本PTA全国協議会からの脱退を決めたところもあります。毎年納入が実質義務化されている割に、その成果が実感できないからでしょう。
そもそもPTAの起源はどこにあるのでしょう。このことについて日本PTA全国協議会のホームページには次のように示されています。
「日本のPTAは、米国教育使節団報告書から始まった」ものであり、「アメリカは、日本社会の徹底した民主化を図るため、戦後いち早く教育専門家を派遣し、その基盤となって社会を支えてきた教育について抜本的な改革を進めようとした。」「使節団は、昭和21年(1946年)3月に来日し、早くも4月7日に報告書を発表し」この中で、PTAに関し次のようにふれている。」
「教育といふことは、言ふまでもなく学校のみに限られたことではない。家庭、隣組その他の社会的機構は、教育において果たすべき夫々の役割を持っている。新しい日本の教育は、有意義な知識をうるために、できるだけ多くの資源と方法を開拓するよう努むべきである。」と、教育に果たすべき家庭の役割の重要性をうたっている。」
「GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)はこうした基本方針を元に、一般成人に対して民主主義の理念を啓蒙することが、新生日本の政治基盤形成上、あるいは占領政策の目的達成上不可欠の要件であるとして重視し、そのための有効な方途としてPTAの設立と普及を奨励する方針を掲げた。GHQの方針を具体的に推進したのは、中央においてはCIE(民間情報教育局)、地方にあっては地方軍政部であった。CIEは文部省を通じて、全国的にPTAの指導、・支援を行ったが,地方では、地方軍政部の指導が大きかった。地方軍政部は制度的にはアメリカ太平洋陸軍総司令部に属するが、実質的にはGHQの下、地方段階で占領政策の実施に当たり、その状況を監視する機関として機能した。

任務の中には、民主的に創設され行動する専門協会とPTAの発展をはかること、PTA会合のために学校施設の利用を促進すること、が掲げられており、地方での実地のPTAの普及・指導に大きな役割を果たした。」(下線は引用者による)
長い引用となってしまいましたが、ここに記載された内容には「努むべき」という表現でもわかるように、あくまでも「努力義務」だったと解釈するのが妥当でしょう。しかし、戦後すぐの段階でアメリカに盾突くようなことはできるはずもなく、全国の学校にPTA組織が広がったことは容易に想像できます。
「努力義務」には強制力がありません。PTAの組織をつくることも、そこに加入することも任意であるわけです。この任意性が、PTA離れの背中を押しています。
つまり、PTAが任意の団体であるにもかかわらず、実質的には強制的に入会させられることに理不尽さを感じる人が増えてきたということです。多くの学校では今でも入会届すら求めていないでしょう。入学したら自動的に会員になるのが常識のようになっています。
それでも、PTA会員になってよかったと思えるとか、入会して当たり前だという共通認識があれば、問題にはなりませんが、今は、そのどちらもが揺らぎ始めています。それが、PTA問題の中核です。
例えば、PTA活動を行うには中心的となる役員を決める必要がありますが、共働きが増え、専業主婦の人が減ったことによって、PTA役員として決められた会議や行事の準備に駆り出されることが物理的に無理であったり、苦痛と感じたりする人が増えています。中には、PTAの会議に出席するために仕事を休まなければならないことも起きてきます。給与支払いが時給計算となるパート勤務などの場合は、特に拒否反応が強くなって当然です。近年の貧困化問題を考えても、家計に影響が出てしまう役員にはなりたくないというのが本音でしょう。また、親の介護などで夜の会議に出席できない場合も考えられます。
それでも役員は決めなければならないわけですから、そこに何らかの無理が生じます。学校によっては立候補者がいなければくじ引きによって強制的に決めるところもありますし、選挙の結果をもって有無を言わせず決定するところもあります。そうなると、決められた方は、押しつけられたと感じることになります。学校によっては、学級懇談会を開き、引き受けられない理由を表明できるようにしているところもありますが、これもなかなか難しい。どこまでを妥当な理由として認めるかという基準がはっきりしないからです。PTAの規約に詳細な基準を示している場合もありますが、それでも、他の人の前で家庭の事情を表明しなければならないとなると、かなりの苦痛です。「そんなこと理由にならないでしょう」という周囲の雰囲気の中で、泣きながら訴えざるを得ない人もいます。
また、個人情報保護法を盾に理詰めで抵抗する人もいます。個人情報はそれを求める者(組織や団体)が利用目的をあらかじめ対象者に明示することが義務づけられています。そのため、PTAが個人情報を得るためには、PTAが利用目的を明らかにしたうえで、独自に情報を収集するべきであるというわけです。PTAの活動を行うために学校から個人情報を得るのは漏洩に当たり、違法行為だという主張です。

PTA活動はこれまで、学校や教育委員会では十分に対応できない学校運営上の事柄を陰で支える役目をしてきました。登校時の児童生徒の安全を守るための見守り(立ち番)活動や公費では対応できない費用の捻出(備品購入を除く)などはそれにあたります。
また、PTA役員は保護者の代表として保護者の意見を学校運営に反映させる場としての機能を果たしてきたことも見逃せません。価値観が多様化する中にあっては、気づかないうちに学校と保護者の間の感覚のズレが大きくなってしまうこともあります。そんなとき、PTA会長や本部役員を通して学校に申し入れを行うことができるわけです。
そういう意義があることについて、これまで学校は十分に説明してきたでしょうか。PTAは学校が責を負う組織ではないとはいえ、どこか、PTAは「あって当たり前」、「保護者であれば会員になって当たり前」という意識があったことは否めないのではないでしょうか。もしかしたら、「最近の親は、学校に世話になっているという感謝の気持ちがない」と嘆いていた部分もあるのかもしれません。そうした姿勢が、社会の多様化や私事化の影響を受けて露わにされた結果、会員になりたくないという人が増えている原因の一つとなっているのではないかと思います。
対策としては、任意であることを前提にしながらもPTA会長や学校長が積極的にその意義を訴えることが、まず、第一でしょう。そして、組織のあり方を柔軟に考えることも必要です。
例えば、入学説明会において新入生の保護者に向けてPTAの存在意義を説明し、同意書を提出してもらうようにすることも考えられます。「そんなことをしたら、PTAに入らない人が増えて活動ができなくなる」という人もいるかもしれませんが、このまま何もしなければ、おそらく、今後数年から10年くらいの間に、さらに入会拒否が増えていくだけだと思います。今なら、まだ多くの人の賛同は得られると思います。先手を打つためにもすぐに実行すべきでしょう。
また、PTA活動をエントリー制にすることも考えられます。すでにある小学校では実践に移しているそうですが、行事や各種の取組ごとに協力者を募るというやり方です。これなら強制感は軽減されるでしょう。活動に協力する人が少なければ、意思を表明した人数で実行可能なことを考えればいいのです。
ただ、このやり方は入会の任意性の問題を解決する手段とはなりません。根本的に改善しようとするなら、思い切ってPTAの看板を外し、「保護者会制度」にするという方法もあります。そもそもPTAの「P」は保護者、「T」は教員ですから、「保護者会」とすることで、学校から独立した組織であることが明確になります。そうすれば、活動は保護者が主体的に決めることができます。また、保護者である限り自動的に入会させられても違和感は軽減されるでしょう。小規模の学校では、創立当初から実施しているところもあります。
ともあれ、今、PTAの本質が問われています。PTAにしかできないことは何かについて、学校、教育委員会も含めて考え直す時期を迎えていることは確かです。
(作品No.181RB)