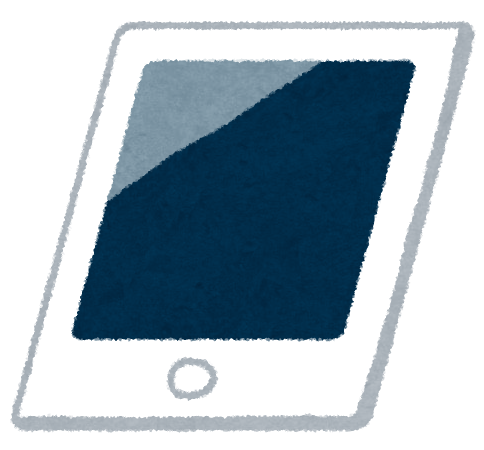中島みゆきさんの「世情」という歌があります。その歌詞に「変わらない夢を流れに求めて」というのがあるんですが、私は長く「変わらない夢を流れにも止めて」だと思っていました。1978年リリースということですから、少なくとも私は高校生にはなっていたはずです。なんともお恥ずかしい話です。
この曲は、当時大人気だった学園ドラマ「3年B組金八先生」(武田鉄矢さん主演)の中で加藤君という生徒を中心とした「反抗的」な生徒が数名教室に立てこもり、最後は警察によって強引に引きずり出されるという場面のBGMとして使われて話題になりました。
担任役の武田鉄矢さんが、廊下でもみくちゃにされながら必死に警察の介入から生徒を「守ろう」とする場面と、この歌の歌詞一つ一つが見事にシンクロしていました。特に「シュプレヒコール・・・」のリフレインは、中島さんの一種「ドス」の効いた迫力ある歌声によって見ている者の胸をぐいぐいと押してきました。そして、日本中を大きな感動の渦に巻き込んだのです。
今思うと、当時の教育はとても「牧歌的」でした。
1970年代から1980年代といえば「校内暴力」が全国に広がっていた時期であり、学校の治安を守るために警察を介入する学校もありました。
しかし、いわゆる「非行少年」の暴力や破壊行為は「犯罪」であるというより「わかってくれよ、先生」という悲痛な叫びとして解釈されることが多かったように思います。
尾崎豊さんの「15の夜」がリリース(1983年)されたのもちょうどこのころです。
「盗んだバイクで走りだす(立派な犯罪ですが・・・)」けれど行き先は自分にもわからない。でも、締め付けるばかりの学校や教師のやり方が、かけがえのない自由を自分たちから奪っていくことは許せない。免許を取得することもバイクに乗ることも許されない。だから盗むしかない。他に方法が見つからない。でも、俺たちは自由のために本当は何をどうすればいいんだ。当時の「暴力」や「非行」にはそんな若者の切ない思いが含まれていました。
戦場とも言える学校。それを敢えて「牧歌的」と表現したのは、教師は非行に対して厳しく接しながらも根本的に教育は信頼関係によって成立するものだという信念があり、警察に頼ることは教育の敗北だと考える人が数多くいたからです。
多くの教師は「俺がなんとかしてやる」という熱い思いで生徒にぶつかっていき、社会もそういう「熱い」教師を支持する土壌がありました。
「お前たちの気持ちはわかる。しかし、許されることと許されないことがあるんだ」という教師の思いが、そこに厳然としてあったのです。金八先生のドラマのシーンが「名場面」となりえたのも、どこかで互いに求めあっているはずだ「牧歌的」なつながりがあったからでしょう。
私が新任として採用されたころ、校内暴力は都市中心から地方中心に移行していました。ピークこそ過ぎてはいましたが、校舎の二階から机が「降ってくる」とか、中庭をバイクで走り抜けるといった暴挙もまだたびたび起こっていました。それでも先輩の先生方は「きっといつかわかってくれる」と生徒を信じて生徒にぶつかっていきました。そして、卒業して何年経っても互いに連絡を取り合うような濃密な信頼関係が成立したのです。
当時、そうした教師と生徒の関係の築き方ができたのは、「情熱」と「信頼」を目に見える形で訴えることができる「牧歌的」な時代だったからだと思います。
そして「牧歌的」な教育を社会で共有可能な目標が支えていたのです。社会学者の土井隆義氏は次のように述べています。その頃の日本は「頂上へ向かってひたすら山を登っている最中」1)であり、人々はその目標を信じていました。だからこそ生徒は反抗する対象を見つけやすかったし、教師は正しい道に戻してやろうとぶつかっていくことに疑問を持たずにいられたのです。
今の学校が難しいのは、こうした共通の目標が社会の中に見つけにくくなったからです。先ほどの土井氏は見田宗介氏の比喩を用いて、「人々はすでに頂上に達しており、広い「高原」にいる状態だ」2)と指摘しています。
「高原」は見晴らしもよく、自由に走り回ることもできます。しかし、今までみんなで見ていた同じ目標はそこにはなく、それぞれがそれぞれに違う方向を見始めています。
そこには「本当はこっちを向いた方がいいんですよ」と自信を持って教えてくれる人はいません。誰もが何を見るのが正解なのかがわかっていないからです。
そうなると一人一人の不安は大きくなっていきます。「本当にこれでいいのか」「もっといい方向はないのか」という不安は尽きることがありません。
私たち教育に関わる者に求められるのは、まず、今私たちが「高原」にいることを受け容れることです。だだっ広い高原で今まで通りに「上を見ろ」と言っても、そこにあるのは広い広い空と雲だけです。言われた方は途方に暮れてしまいます。

冒頭の「世情」には次のような歌詞があります。
「時の流れを止めて変わらない夢を見たがる者たちと戦うため」
これまで戦ってきた相手はもうここにはいません。時の流れを止めようとしても無駄です。戻ることは許されないのです。教師や学校が「変わらない夢を見たがるもの」になってしまえば、子どもたちは路頭に迷うだけでしょう。私たちはいまこそ「問い」の仕方を変えなければいけません。広い高原の中で、迷っているのは子どもたちだけではないはずです。
肩の力を抜いて「さあ、どっちにいこうかねえ」と、子どもの横にゆったりと寄り添わなければなりません。
そう考えると私の「変わらない夢を流れにも止めて」という聞き間違いは、あながち間違ってはいないのかもしれません。今までと変わらない目標を子どもに押し付けるのではなく、大きな社会の変化の中でさえも敢えて自分を「止めて」、子どもと一緒に考える。悪い話じゃないと思います。(作品No.129RB)
1)https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87010?imp=0
2)土井氏は『「宿命』を生きる若者たち』(2021 岩波ブックレットp38)で、見田宗介氏の比喩を次のように引用しています。「見田宗介の巧みな比喩を借りるなら、現在の私たちはすでに山を登りつめて、高原地帯を歩みはじめているのです。」