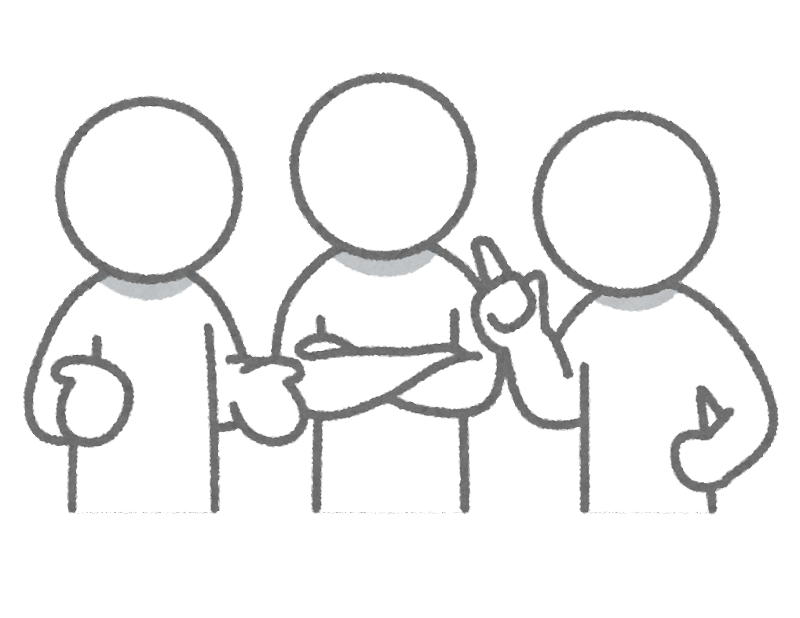―教員の不祥事について考える その1ー
社会の中で体罰が問題視されたのはいつごろからなのでしょうか。今は誰に聞いても「体罰は良くない」と答えるでしょう。かつては「愛のムチ」だと言って容認していた時代もありましたが、今そんなことを言ったらそれこそ「愛の無知」と非難されるでしょう。
しかし、依然として体罰はなくなっていません。つい先日もある私立高校で部活動の顧問が、試合当日にユニフォームを忘れてきた部員(高校1年生女子)の頭を殴り、それによって女子生徒の顎が外れるという大きな傷害を負わせました。しかも、そのまま5時間以上自分の側に立たせて罵詈雑言を浴びせ、次の日も臀部を減るなどの暴挙に出たというのです。生徒は精神的にショックを受けて学校に通えない状態であるということです。ここまでくればもう暴力を越えた暴行であり、生徒がケガを負った以上は「傷害罪」が適用されても何の不思議もないでしょう。いや、むしろそうすべきです。
そもそも、これだけ連日のように教員による暴言や体罰が報じられ、教員が処分されているにもかかわらず暴行に及んだわけですから、明らかに「確信犯」です。今後、被害届が出されると思いますが、その前に学校は当該教員を懲戒解雇処分(私立高校ですから、理事長の判断でできるはずです)とすべきでしょう。被害者からすればそれでも足りないくらいです。とにかく、教師としての資格があるとは到底思えません。
と、ここまで書いてきて読者の皆さんは「あれっ」と思われたでしょう。タイトルと内容が微妙にかみ合っていないんじゃないの?と。
実は私は、現代においては有形力の行使(殴る、叩く、蹴るなど)としての「体罰」は存在しないと思っています。なぜなら、有形力を行使した時点でそれは「体罰」ではなく「暴行」だからです。「体罰」という言葉を使うから、どこか教育的配慮というニュアンスを残してしまうのです。
私は以前、「体罰」について若干研究のまねごとをしたことがありますが、意外と「体罰」の定義は、はっきりしないまま放置されてきたのです。学校教育法第11条には、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」とされていますが、そういう割には「体罰とは何か」という定義は示されていません。他の法規にも明記されていないのです。懲戒と体罰の境界については、通知レベルでしかありません。しかもそうした通知は、過去の裁判の判例をもとに書かれていることが多いのです。「体罰」とは何かという明確な定義を法的レベルで明示せず、最終的な判断を司法に委ねてきたという意味で、文科省の怠慢と言ってもいいのではないかと思います。
私は「体罰」という言葉が使用できるのは、その行為が「体罰」かどうか微妙な場合に限られると思っています。例えば、何か良くないことをした生徒を別室に呼んで説諭しようとしたところ、説諭が終わらないうちに当該生徒がその部屋から勢いよく立ち去ろうとしたとします。教員とすれば「まだ話は終わっていない」と思って当然でしょう。そして、教員が生徒をその場に引き留めるために、逃げようとする生徒の腕をつかんだとします。そのとき、教員の手の跡が生徒の腕についてしまったといった場合、それを有形力の行使と言えるかどうかは微妙な状況となります。文科省は「有形力の行使」を体罰の筆頭のように扱っていますが、有形力を行使したらもう「体罰」の域を超えているのです。だから「体罰」という言葉が使えるのは、それが有形力の行使に当たるかどうかを見定める余地があるときに限って、「便宜上」用いられる概念だと思うのです。
しつこいようですが、有形力の行使は明らかに暴行であり、相手がけがをすれば傷害罪のレベルになります。後は、その行為の程度によって処罰の内容が決められるだけです。だから、「これは明らかに「体罰」である」という言い方は、そもそも日本語として成立しないのです。こういう言い方をした時点で、暴行に教育的配慮という保護膜を施し、曖昧にしようとしているのと同じことです。

そういう中途半端な部分を残している上に、有形力の行使をした教員は多くの場合懲戒免職とはなりません。それどころか暴力をふるった教員は、顔写真はもとより、名前すら公表されないこともあります。名前や顔を公表しないのは、ほとぼりが冷めれば他の学校などで教員として出直す道を残すためなのではないかと勘繰ってしまいます。そもそも、傷害罪を問われるようなレベルの暴力をふるっておきながら、私立学校なら理事長、公立学校なら都道府県教委の課長クラスら数人がテレビの前に立って深々と頭を下げること自体が不自然です。確かに採用したそれらの人の責任はあるでしょうが、これだけはっきりした事例であれば、本人も同席すべきでしょう。だいたい、一般企業に勤める人が無抵抗の同僚や後輩を顎が外れるくらい殴ってけがを負わせ、出勤できないほどの精神状態に追い込んでいる状況で、加害者が警察に連行されるかされないかくらいのタイミングで謝罪の記者会見などさせてもらえるでしょうか。刑が確定していないのに何を謝っているのでしょう。しかも、そこにいるのは上司なんてこと世間ではあり得ません。
学校という組織は、教育委員会を含めて身内に非常に甘い。一昔前の校長は、何かしら不祥事があったときにいかにして当の本人を前に出さないかを一番に考えていました。それが職員を守ることだと信じて疑わなかったのです。そしてそういう校長が「親分肌」の校長として慕われてきたのです。今でも多くの校長がその感覚を残していますし、教員も守ってくれる校長を当てにしているところがあります。そして、「校長が何とかしてくれるだろう」という甘えた教員が生き残るのです。熱心にやった結果なんだから何とか助けてやるのが「親分」の役割だというわけです。
私は、かつて教頭のとき暴言が止まらない臨時講師(当時は半年経過し時点で、一日空白をあけて再度採用するという制度でした)を校長と相談して更新しなかったことがあります。普通なら警察にでも捕まらない限り更新するのが通例です。しかし、あまりに目に余ったので校長と相談の上、決断しました。そのあと、本人はもちろん、同じ職場の同僚や地方議員、引退した元校長などから「自分の学校の教員くらい守れないのか」と罵声を浴びせられました(当時の校長はもっとひどかったでしょう)。その中には、私の中学校時代の恩師もいました。とても悲しかったのを覚えています。あんなに頼もしかった先生も現実が見えなくなっている、そのことがとてもつらかったのです。
私は今でもそのときの判断は間違っていなかったと思います。有形力の行使こそなかったものの毎日烈火のごとく怒鳴り散らされ続けている子どもたちを放っておくことはできませんでした。子どもたちは、学級担任であるその教員の顔を見るだけで固まってしまうほど恐れていました。学校関係者から聞こえるのは非難の声ばかりでしたが、保護者からは感謝されました。そして、なにより子どもたちに笑顔が戻りました。職員を守っていれば、少なくともあと半年、子どもたちは死ぬ思いで登校を続けなければならなかったのです。
昔はそれでも何とかなったかもしれません。でも、今は違います。そういう守り方をすればするほど不祥事を起こした教員にバッシングが集中し、それを許した校長に無数の矢が飛び、他の教員も信用を失い、学校不信は取り返しがつかないほど深刻になってしまいます。しかし、そういう管理職は今でもたくさんいます。まるで教員が第一に守るべきは生徒であるという基本を忘れてしまっているかのようです。
また、私は小学校の校長をしていたとき、保護者からパワハラやセクハラまがいの言動で子どもが追い詰められているという訴えを受けました。私はそのときその教員にはっきりと宣言しました。「あなたは自分にはやましいところはないと言いますが、保護者が泣きながら訴えてきているのです。その事実を真摯に受け止めなさい。もし、明らかな証拠が出た場合には、私はあなたを守ることは一切しません。」と。
その教員はちょうどその年、定年退職を迎えるタイミングでした。当然私よりも年上です。その教員はその後、私を「パワハラ校長として訴えてやる」と陰で息巻いていたそうです。しかし、私は教育委員会にいたので知っていたのです。その教諭が、10年ほど前に同じような問題を起こし、保護者が教育委員会に被害を訴えていたにもかかわらず、教育委員会は何の処罰も与えず、教員を転勤させるだけでうやむやにしていたことを。そして、そのときの記録が教育委員会のどこに保管されているかも知っていました。訴えればその資料を裁判所に提出するつもりでした。当然その教員も私が教育委員会にいたことは知っています。だから、どんなに息巻いていても絶対に訴えることはないという確信が私にはありました。その資料の内容が公になって一番困るのはその教員です。そうなれば、下手をすれば目の前の退職金すらすべて没収される可能性もあります。そこまで覚悟して訴えるほどの度胸がある人間なら、こそこそとセクハラまがいのことはしないでしょう。
この教員を野放しにしてしまったのは10年前に厳罰(懲戒免職までは無理だったとしても)に処しなかったからです。そうしていれば、その後被害に遭う子どもを生み出すことはなかったかもしれないのです。そのツケを私は払わされたのです。こんな腹立たしいことはありません。だから、その学校に赴任が決まった時点で「どこかではっきりさせてやる」と決めていました。それまでの管理職は学級担任から外したり、固定された特別教室での授業に専念させ、できるだけ複数の教員を授業に配置するなどさまざまな手立てを打ってきたようです(複数の学校をたらいまわしにされていたようですが)。加配もさほど多くなかった当時は慢性的な人員不足でした(今も解消されていませんが)。学校現場にとって、これほど迷惑な話はありません。また、児童が特別教室と一般の教室移動の行き来する場合も必ず別の教員を先導させるなど校内のルールも変更したそうです。何より、セクハラ疑惑があることを他の教員は知っているわけですから、何かあれば職員全体が管理職に攻撃の矢を向けることも考えられます。そうなると学校は空中分解してしまいます。
実際、私がその学校に赴任するまで何度も怪しい雰囲気があったそうですし、保護者から苦情も結構あったようです。しかし、それまでの管理職は、総じて腫れ物にさわるように対応してきました。真っ向から攻めることを避けてきたのです。だからいつまでたっても同じようなことをいろんなところで起こし続けて、そのたびにしらを切り続けてきたのです。
私がその教員に宣言した際、同席した教頭が終わったあと若干心配そうな顔で「あそこまではっきり言う校長には出会ったことがない」と言われました。そして、その話は職員の間に広がりました。「今度の校長は本気だ」という雰囲気が生まれました。だから、問題が起きたとき躊躇なく私に報告してくれたのです。私は保護者の了解を得て、その日のうちに本人を呼び出して宣言したのです。自慢みたいになってしまいますが、そのスピード感は大成功だったと今でも思います。ちょっとでもためらう様子を見せたら、職員の気持ちは離れていくに違いないと思いました。だから、本人との対応も管理職だけで行いました。学級担任をはじめ他の教員を介入させることはしませんでした。そんなことをしたら、同席した職員にどんな被害が及ぶかわかりません。
実は、私はその学校に赴任してすぐに、セクハラ疑惑の教員を校長室に呼び出して「宣戦布告」をしていました。本当はそこまでしなくてもよかったのですが、本人が私の顔を見るたび「再任用頼みますよ」としつこく言ってきたのです。正直、頭にきました。「ああ、やっぱり何も反省していない」ということがはっきりしたのです。私は校長室で言いました。「私がこの学校に来たのは、あなたを無事に定年退職させるためだ。しかし、それはあなたのためではない。あなたが無事に定年退職するということは、あなたが何も問題を起こさなかったということだ。どうか私の期待に背くことはしないでほしい。」
その教員はかなり不満そうな表情で、どうしてそんなことをわざわざ言われなければならないのかと反論してきましたが、「今、私が言ったことがすべてです。」として取り合いませんでした。先に書いたように、案の定問題は起こりました。本人は最後まで否定を続けました。本当は私はその教員に辞めてほしいと思っていたのですが、しばらくして被害者側の保護者があきらめてしまいました。これ以上、事を大きくしないでほしいと言ってきたので処分までは至りませんでした。夫婦そろって校長室に来られたときのご両親の苦渋の表情が忘れられません。親としては、これ以上事が大きくなれば本人(娘)がさらに傷つく。もし、被害者として名前が知れるようになったら娘のためにはならないとおっしゃったのです。そこまで言われて、一緒に最後まで戦いましょうとはさすがに言えませんでした。でも、私の対応には感謝してくださいました。結局その教諭は最後まで勤め上げました。教育委員会にも始終情報を伝えていましたが、明確な証拠がないため具体的な対応ができなかったという事情も分からないではないので、特に教育委員会にいやごとは言いませんでした。
教員の不祥事は、子どもが被害者となっていわれのない苦しみを与え、学校に対する信頼を失墜させるだけではありません。こういうことが続けば、今の学校が抱えている問題の本質すら曖昧にしてしまうのです。
私は、現在の学校の多くの問題は学校の制度疲労が原因だと思っています。まじめな教員ほど、制度疲労を起こした学校制度と現実に起こる問題との狭間で苦しんでいます。特に、学級制度はもう限界に達しています。学級は、明治24年(1886年)の「学級編成ニ関スル規則」で初めて法的根拠を得ました1)。今もこれを根拠としているかどうかはわかりませんが2)、このときにそれまで採用されてきた「等級制」を廃止してほぼ今の学級の形が成立しました。100年以上同じシステムが続いているのですから「制度疲労」が起こっても不思議ではありません。とにかく、強制的に所属する学級が決められ、それを変更する要求はよほどでない限り認められない超閉鎖的な空間の中で、いじめられた子が行き場を失い、不登校の子が復帰するきっかけを失っています。教員はその子を何とかしようと懸命に頑張りますが、いじめにしても不登校にしても学級制度があまりに頑強であるために解決の道は閉ざされているのです。学級がせめてもう少し柔軟な組織であれば、普段から子どもたちにさまざまな居場所をつくることができます。大学では深刻ないじめは小中高に比べて非常に少ないといわれています。それは、集団が固定されていないからです。自分と合わない者がいても、嫌がらせをしたとしても、それが限定された場と空間で済むからこそ問題は深刻化しないのです。強固な学級制度のままでは、いじめられた子の戻るところは元の学級しかありません。悲劇的なのは、そういう子どもたちが学級に入れないことを次第に自分の責任だと自分を責めるようになることです。こんな理不尽が許されていいはずはありません。
だからこそ、本来ならば、文科省はもちろん、教師や生徒、教育委員会、そして保護者や地域が一丸となって、本当の意味で子どもにとっていい学校(学級)とはどうあるべきかを考えなければならないのです。それなのに、犯罪まがいの行為をする一部の教員がいることで、本質的な問題を論じることが困難になってしまいます。つまり、「システムがどうのこうのという前に、教員の問題行動を何とかする方が先だろう」とか「教員の責任をシステムせいにするのは詭弁だ」という見方が広がってしまうからです。そういう意味でも、明らかに有形力の行使をした教員は、即刻公の場に出し、警察に介入してもらって徹底的に捜査するべきです。学校の中だけで対応しようとするから、問題を長く引きずることになり、さらに学校不信は深刻なもとになって、本当に必要な議論ができなくなってしまうのです。
いまや学校は、一部の問題教員にかまっているような余裕はありません。冷たい言い方かもしれませんが、教員を特別視することなく、一般の人と同じ手順で「処理」すべきです。
ただ、一つ気になることがあります。それは、次回に。
- 寺﨑昌男・平原春好編(2002)『新版教育小事典』(学陽書房、p37)
- この点についていろいろ調べたのですが、いわゆる標準法も学習指導要領も当然生徒指導提要も学級の定義は明治24年の「学級編成ニ関スル規則」以外には見つけられませんでした。そこで、文科省に直接電話して聞いてみたのですが、後ほど私の携帯に電話しますと言われて、もうそろそろ一か月が経とうとしています。
(作品No.170RB)