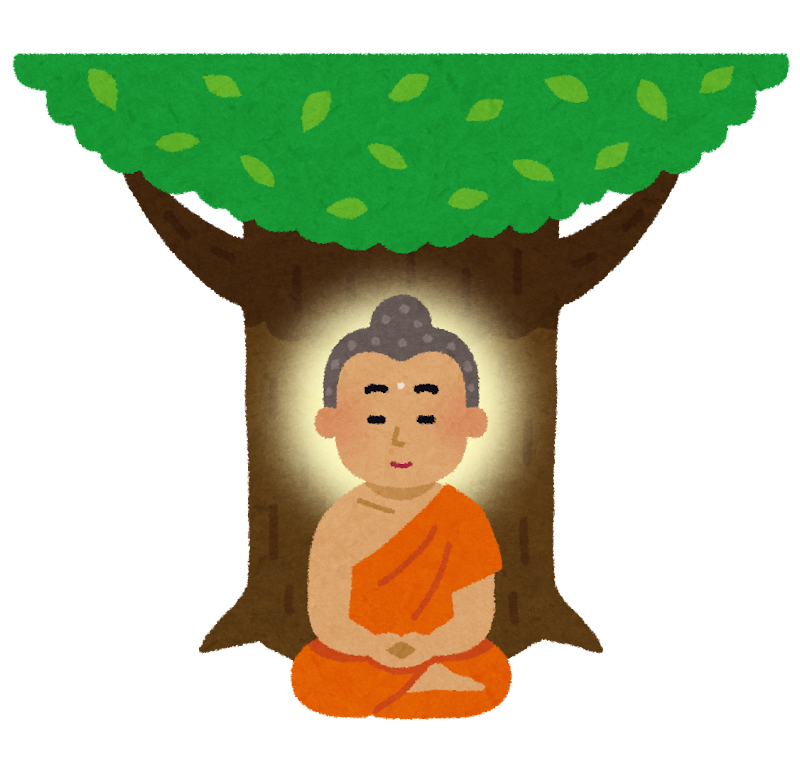私は、車を運転中にラジオをかけることが多いのですが、その内容をすべて聞いているとは限りません。音声は発信されて、空気に振動を与え、私の鼓膜を震わせてはいてもまったく内容を覚えていないことがあります。どうしてこんなことが起こるのでしょう。
そもそも、人が音を認知するとき、音を出したものが空気を振動させ、私の鼓膜を動かします。そして、その振動は中耳から内耳に伝わり、中耳の中にある液体のようなものを通して内耳の組織に伝わり、最終的に脳に電気信号として送られることで「聞こえる」という状態となります。だから、本来ならばすべての音が脳によって認識されてもおかしくないわけで、そうなると「聞こえているはず」なのにまったく記憶に残らないということは起こらないはずです。
「私たちは常にさまざまな音を聞いていますが、その中でも『注目すべき音』と『聞かなくてもいい音』を脳が区別して、大事な音に注意を向けて、理解し、記憶しているのです。」1)
つまり、私たちは「今、ここ」における自分にとって興味や関心、必要性のレベルによって「聞く」か「聞かないか」を判断(無意識のことも多いでしょうが)しているというわけです。このときの「判断」は個々人の興味・関心などの度合いによって為されます。現象学的社会学の祖と言われるA・シュッツはこれを「レリバンス」と名付けました。人は見ているものに対する重要性の度合が違うので、それを「大切だ」と感じる人(こと)もあれば、ほとんど記憶にさえ残らないくらい無関心だったりするわけです。
私たちはしばしば「聞く」と「聴く」の違いを通して、子どもに「聴く」ことの大切さを伝えてきました。それは、「聴く」ことが「聞く」ことに比べて高い「レリバンス」を必要とするからです。よく「心で聴く」といわれますが、それは話し手に対して最も高い「レリバンス」を発動している状態なのです。
子どもが教師に対して高い「レリバンス」を発動するためには、教師が子ども以上に高い「レリバンス」をもって接することが必要となります。
マザーテレサが「愛の反対は憎しみではなく無関心です。」と言ったというのは、あまりに有名な話です。彼女が世界のいたるところで起こっている悲劇に目を向け、言葉を発することで、悲劇に苦しむ人にその思いが伝わり、多くの人が苦しみの中でさえ彼女に高いレリバンスを発動し、前向きに生きようとする力を生み出すのです。
マザーテレサほどの人格者になるのは至難の業ですが、目の前の子どもが自分にとってどのくらい重要な存在であるかということを絶えず確認することは、誰にでもできるのではないかと思います。(作品No.203RB)