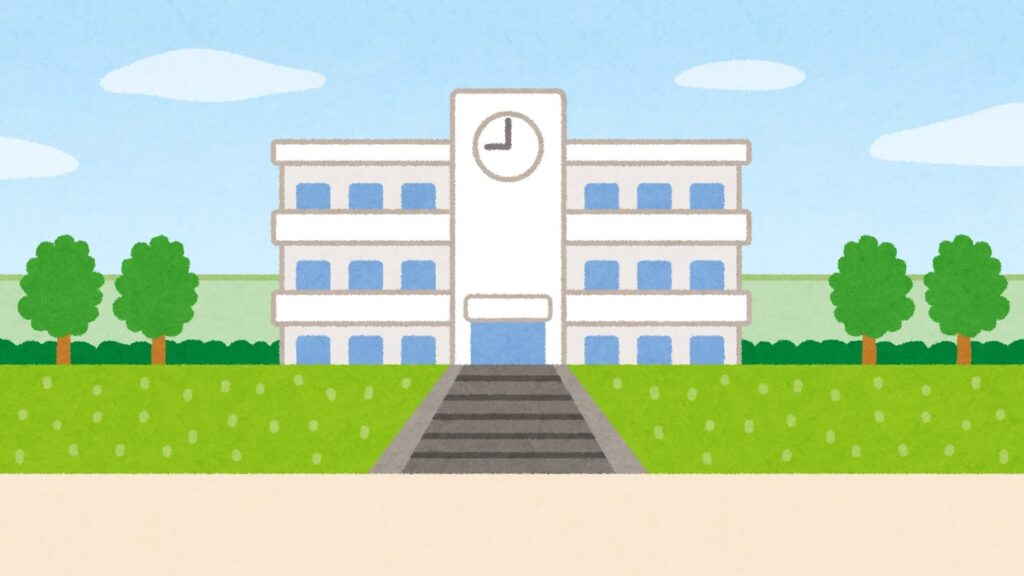夏休みの終わりごろ、いつも考えていたのは「始業式に子どもは来てくれるだろうか」ということでした。
8月の最後の週あたりに「中学生が自ら命を絶った」というニュースが報道されたりすると、もう気が気ではなくなります。正直言って「こんな報道はやめてほしい」と何度も思いました。報道の自由が大切なのは百も承知ですが、こういう報道に煽られて追随する子がいたらどう責任を取ってくれるのかとさえ思いました。そして、瞬時にいろんな子の名前や顔が頭に浮かんでくるのです。最後は「学校には来られなくてもいい、生きていればそれでいい。生きていれば何とかなる」と祈るような気持ちになります。
「2022年の一年間に自殺した日本の若者(小学生から高校生)は514人に上り」、国は今年4月に発足した「子ども家庭庁」(以下、家庭庁)に「自殺対策室を設置」し、6月には「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(以下、連絡会議)が「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめ」ました1)。
すでに学校には、スクール・カウンセラーやスクール・ソーシャルワーカーなどの専門家が配置され、児童生徒の心のケアをしてもらえるようになりました。しかし、「周りの大人がこれだけクモの糸を垂らして、『相談してね』と呼び掛けても、子どもは来ない、来ることができない」2)状況が続いています。24時間365日誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口「あなたのいばしょ」(NPO法人)理事長の大空幸星氏によれば、寄せられる相談内容の多くが学校に起因したものだといいます(学校の責任だという意味ではありません)。
大空氏は家庭庁の連絡会議に有識者の立場で参加し、自殺対策の課題として「スティグマ」からの回避を挙げています。一般に「スティグマ」は烙印という意味ですが、ここでは「思い込み」に近いと考えた方がいいでしょう。大空氏は次のように指摘します。
「『相談することは恥ずかしい』『相談したら負けだ』『大人にはどうせ分かってもらえないじゃないか』と子どもたちは思っている」「スティグマは文化なので、仕組みや教育で変えられる部分もあると思うが、いくら相談の受け皿を増やしても、この部分が変わらない限り難しい。」3)
私たちがいくら子どもに寄り添おうと努力しても「文化」としてのスティグマの前には、いかにも無力です。なぜなら、「文化」には必ず「規範」が含まれ、社会的規範は「世間の常識」に繋がるからです。『相談することは恥ずかしい』『相談したら負けだ』という子どもの声は、「辛くても自分が頑張らなければ何も解決しない」という社会的規範(当たり前とされていること)は、子どもに大きなプレッシャーとなることがあるのです。つまり、「世の中で当たり前だと言われていることが自分にはできない。当たり前を決めているのは大人だ。だから大人がわかってくれるはずがない。」と思い込んでしまう、それが「スティグマ」の正体です。
教育に指示や指導は欠かせません。でも、そのために子どもは教師との関係を「タテ」の関係と捉えがちです。そして「タテ」の関係は変えることのできない「規範」であると思い込み、適応できない自分を追い詰めてしまいます。その状態を緩和するのが、「ヨコ」や「ナナメ」の関係です。「ヨコ」とは「子ども同士」の関係、「ナナメ」とは家庭や学校以外の大人との関係(例えば地域の人や各種相談機関の相談員など)のことです。特に現代では、「ナナメ」の関係は学校が意識して機会を作らなければ自然発生的に築かれるものではなくなっています。
人が本音で相談できるのは、自分をまったく知らない人であることが多いものです。だから、普段の様子が知られていない「ナナメ」の関係の相手には、何の利害関係も上下関係もなく安心してすべて話せるのです。
例えばゲストティーチャーの招聘は、第三者との出会いを生み出すきっかけになるかもしれません。また、「あなたのいばしょ」のような相談機関を紹介することによって、「ナナメ」の関係にある大人が社会の規範としての文化を柔軟に理解していることに気づくかもしれません。そうした気づきが、子どもを救うこともあるのです。
これから起こり得るすべての悲劇を防ぐことはできないのかもしれません。でも、学校という枠組みをほんの少し緩やかにするだけで、どの学校にもできることはあると思うのです。
ちなみに大空氏は、「2学期の始業式を朝からやらなくてもいいのではないか」と述べています。実際に可能かどうかはわかりませんが、要はこのくらい柔軟な発想が必要だということなのです。
1) ~3) 2023年8月22日教育新聞デジタル「子どもの自殺対策 「あなたのいばしょ」の大空幸星さんに聞く」
参考)NPO法人「あなたのいばしょ」ホームページ:https://talkme.jp/
(作品No.230RB)