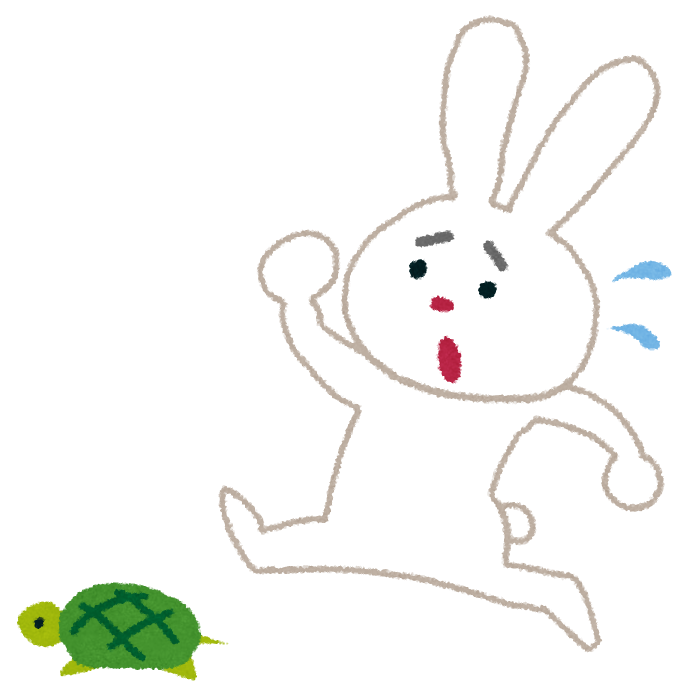文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(令和4年度)によると、全国の小中学校の児童生徒数が112万3945人減少している(2010~2022)にもかかわらず、不登校者数は11万9891人(2010)から29万9048人(2022 過去最高)と、実に17万9157人増加しています。特に、直近の2020年から2022年には10万人以上増加しました。当然、不登校者数が全児童生徒数に占める割合は上昇し、1.13%(2010)が3.1%(2022)と約3倍になっています。不登校が急増している要因を、文科省は次のように分析して(同調査概要)います。
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透の側面等による保護者の学校に対する意識の変化も考えられるが、長期化するコロナ禍による生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況が続いたことや、学校生活において様々な制限がある中で交友関係を築くことが難しかったことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられる。」
また、文科省は、不登校の具体的な理由(2022)として「無気力・不安」が51.8%、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」が11.4%を占めているとしています。このデータはさまざまな研究や論文で引用されています。
しかし、私はこの「具体的な理由」の結果に、かねてから疑問をもってきました。それは、この調査が当事者による回答ではなく、調査における「理由」の選択肢が昔から大きく変わっていないからです。かつて学級担任として生徒の不登校の理由を報告するたびに悩みました。保護者はもちろん、本人でさえよくわかっていないのに、私が選んでいいのかと。
文科省もその辺の矛盾を理解したのか、「不登校に関する調査研究協力会議」を設置し2019年に児童生徒に直接回答を求める実態調査を実施しましたが、残念ながら「回収率はきわめて低かった」1)と言われています。不登校の子どもたちの声を聞くことはそれほど難しいのです。理由がわからないと解決方法も見つかりません。また、本人や保護者も不安が募る一方でしょう。
例えば、「ぶどうの会」(山梨県不登校の子どもを持つ親たちの会)を設立した鈴木正洋・鈴木はつみ両氏は保護者から最も多く受ける質問が「子どもの接し方を知りたい」、「この先どうなってしまうのかとても不安。どうしたらいいのか」であると述べています2)。
そもそも不登校は、登校できないことが問題なのはなく、登校できないことで自らを過剰に責め、自分を否定的にしか捉えられなくなり、最終的に生きることにさえ疲れてしまうところに大きな問題があります。

親も教員も何もできない無力感に苛まれることも多いのですが、やはり、私たちにできることは、当事者の声を当事者のペースで粘り強く聞く耳を持ち続けることだと思います。私たちは職業柄、頭のどこかに「学校は来て当たり前」「来ることが正解」という前提で不登校の子や保護者と接してしまいがちです。確かに、不登校による学力低下や、社会性が十分に身につかないのではという不安はあります。また、進路に影響がないとも言い切れません。その子の将来を考えれば何とか学校に来てほしいと思います。しかし、不登校は「子どもたちの命を懸けたデモだ」3)と言われます。「デモ」の要求はただ一つ。「分からない」ことを「分かってほしい」という思い。どうして自分は学校に行けないのか、どうして人よりこんなに弱いんだ(本当な弱くないのに)、こんな自分に生きている意味はあるのか、頭の中は「分からない」ことでいっぱいなのです。だから、「デモ」を行っている最中に私たちが勝手に「理由」を当てはめることはできません。先に挙げた「ぶどうの会」では、入会時に保護者へ「子どものことは子どもに任せて待ちましょう」と伝えるそうです。これも勇気のいることだと思います。
私たちは「デモ」のきっかけは何だったのかを忌憚なく保護者を交えて職員同士で話し合うことが必要です。そして、その子が「デモ」の最中なのか、始めようとしているのか、終えようとしているのかを見守る視点を持つこと、教員は学校以外にも自分を成長させる場がたくさんあることを示すことです(タイミングは大事ですが)。そして、いつか必ず前を向いて歩きはじめると信じて寄り添うことです。
ちなみに、先般「滋賀県フリースクール等連絡協議会」が滋賀県内でフリースクールに通う不登校児童生徒と保護者に実施したアンケートがホームペーに公開されました。この調査が画期的なのは、氏名は伏せてあるものの、自由筆記がほぼ原文のまま掲載されていることです。同協議会は個人情報保護のため転記や引用を固く禁じているため、ここで内容を紹介することはできませんが、ぜひ勇気を持って、一度確認してみてください。私は自分の不登校に対する意味づけが決定的に変わりました。「命を懸けたデモ」の本当の意味がぐさりと胸に刺さったのです。子どもたちが語る真実の声です。私たちにはそれを聞く責任があります。
1) 『教育』2022年5月号(教育科学研究会、p4)
2) 前掲、p29
3) 吉田田(ヨシダダ)タカシ「【行列のできるアートスクール】 不登校は命を懸けたデモ」2023年8月23日教育新聞デジタル
吉田田タカシ:2022年「トーキョーコーヒー」設立(登校拒否の言葉遊びから生まれた、教育システムを進化させるムーブメント。
大人が楽しく学びあう拠点は全国に約300ヶ所)。