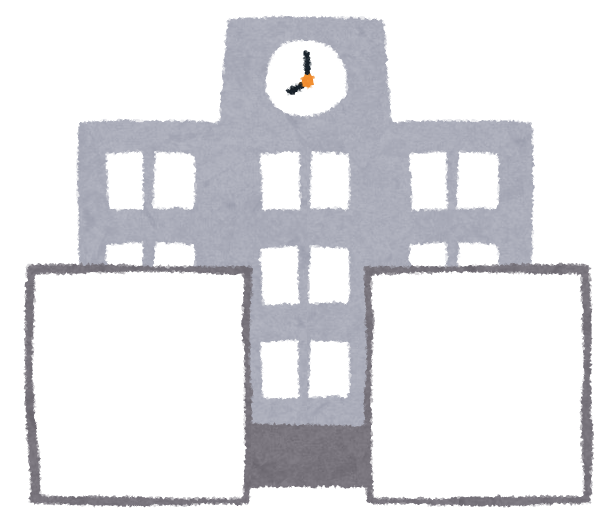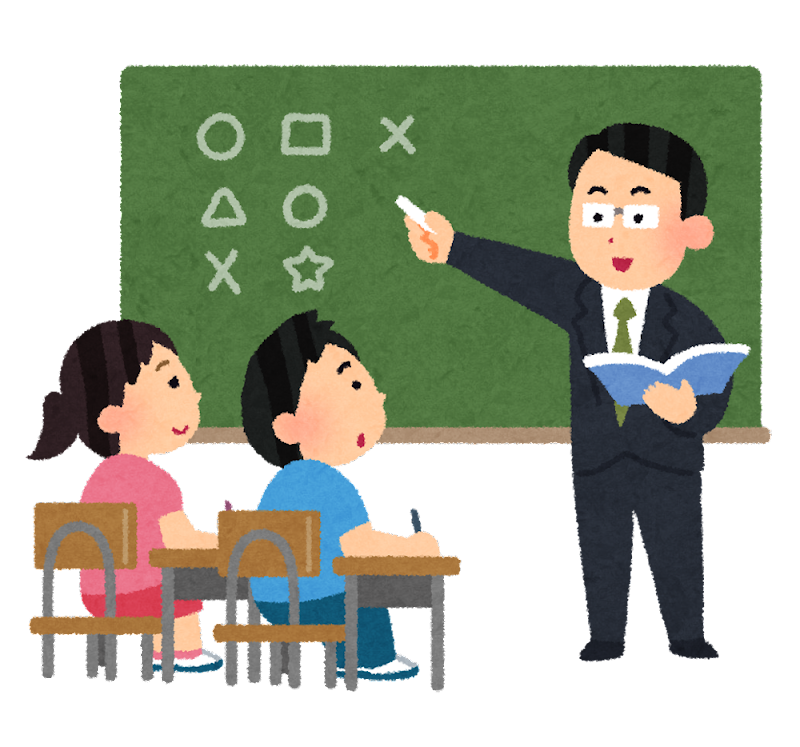全国5か所(和歌山、福井、山梨、福岡、長崎)に展開する「きのくに子どもの村学園(学園長:堀真一郎氏)」では、教科書にとらわれない学びが中心で、宿題もテストもない。通知表は数字による評定ではなく、その子の伸びているところを文章で記述する。30年前の1992年、和歌山県の北東の端、橋本市の山中でスタートした学校です。私立ですが、学校教育法に定められたいわゆる「1条校」でフリースクールではありません。「どうせ小学校だろう」思われたかもしれませんが、ここは小中一貫校です。
同様の「自由」を掲げた私立学校は、全国を探せば結構ありますが、圧倒的に私学が多いのは、制度の縛りが少ないことが大きな理由の一つでしょう。公立中学校なら県立高校の入試制度を県教委が細かく定めていますし、入試問題の大半が選択式です。選択式問題はどうしても知識を問う内容に偏りがちです。そのうえ、複数志願制を導入しているところでは、A高校からB高校へ点数が知らされることがあるため、採点はできるだけ客観的なものでないと公平性が保てません。読解力や情報処理能力を問う工夫はされているようですが、それも限界があります。大学入試で記述式を取り入れると言っていた文科省が直前になって実施を断念したのも客観的な採点が難しいからです(初めからわかっていたことだと思うのですが・・・)。
本年度の高校入試選抜要綱を作成するにあたって、県教委は事前に各地区の中学校長会に意見を求めました。いい機会だと思って当地区の回答は私が書きました。内容は「中学校の教諭は多くの制約の中でアクティブラーニングや探究的な学習に誠意を持って取り組んでいるが、どんなに工夫を凝らした授業をしても、生徒や保護者の多くが公立高校進学を希望している限り、特に3年生では入試問題に対応できる授業を実施せざるを得ない。いくらコミュニケーション能力等が高くとも入試の点数には反映されないような状況では、そういう力をつける授業は「やり損」だと考える教員を納得させることは容易ではない。せっかく小学校で、多くの体験活動を取り入れ、幅広い学力をつけようと努力しているのに、それを十分に発展させる時間がない。何より、教員のモチベーションが上がらない。早急に対応しないと文科省のいう「学力」を身に付けることは到底できない」という内容で文書を提出しました※。今の県の入試制度は学習指導要領の理念とあまりにも乖離が大きいと感じます。

なかなか変わらない公立高校入試とそれに制約される公立中学校では、知識優先の授業から脱するには限界があります。それでも(条件は大きく違っても)、私は冒頭に挙げた「子どもの村学園」のような学校から吸収すべきものはあると思います。その一つが以下に示す堀学園長の言葉です。
「大人はよく子どもに、“自由にやってごらん。でも責任は自分で取るんだよ”と言います。それは、ある意味脅し文句でもあるのです。子どもの村では、“自由にやってごらん。責任は大人が取るから”と言うのです。子どもなりに考えて、勇気を出してやったことも、うまくいかないことだってあります。そこで、“自分で決めたんだから”“一体何やってるの”と言うのは、“どうせ失敗すると思って見ていた”のと同じことです。」(宿題も校則もない「自由にやってごらん。責任は大人が取るから」授業も子ども任せ 「先生」のいない学校 2/12(土) 13:01配信 週刊女性PRIME 下線は引用者)
この考え方には賛否両論あると思います。でも、少なくともこういう考え方もあるという「気づき」を私たちに与えてくれます。その「気づき」が、私たちを「褒めるために指導する(叱るを含む)」という教師の原点に帰してくれます。原点に公私の別はありません。
(作品No.31HB)
※ちなみに、県教委からは何も回答はありませんでした。あるわけないか・・・。