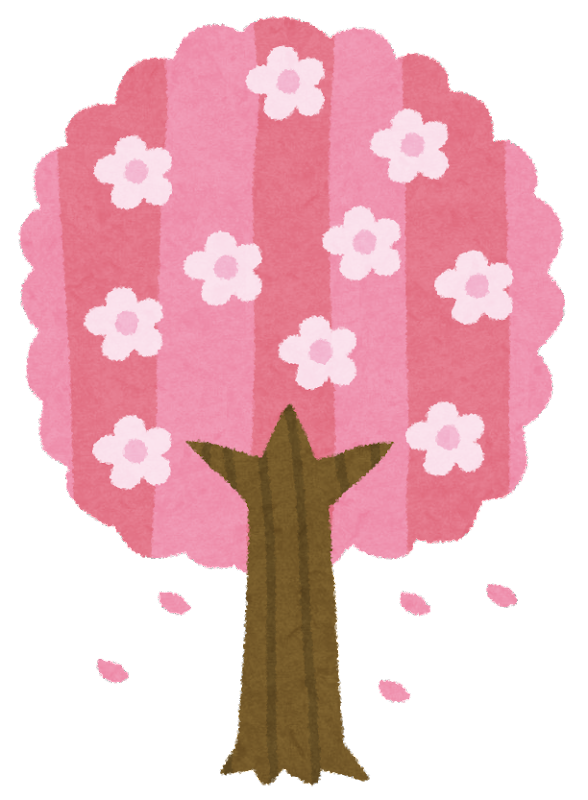最近では、さまざまな場面で「エビデンス」が求められるようになりました。「エビデンス」とは、「証拠、根拠、証明、検証結果」1)のことを指します。人びとを納得させたり、説得したりするときには、客観的な根拠は欠かせません。例えば、病院で医者が患者に「この薬がたぶん効くんじゃないかなあ。」などと「いいかげんな」言い方をしたら、患者は「この医者は本当に大丈夫か?」と不安になるでしょう。そして、今自分に施されている治療も科学的根拠や臨床的な裏づけ、つまり明確な根拠がないのではないかと不安になり、違う病院に行った方がいいかも…と思ってしまいます。患者は医師を信頼し、治療に「エビデンス」があると信じているからこそ安心して治療が受けられるのです。
こうした「エビデンス」は、医療の世界に限らず、さまざまな領域で広く重視されるようになりました。企業の活動においても、学術的な研究論文においても、なくてはならないものです。そして、それらの「エビデンス」の多くは客観的な数値に表されます。
しかし、世の中にはどうしても数値では測れないものもあります。教育の世界ではむしろそうしたものの方が重要であったりします。例えば、クラスの雰囲気がいいとか悪いとかというのは、教室内の二酸化炭素濃度のように機械では測定できません。しかし、不思議なことに雰囲気の良さは、教室前の廊下を通るだけで伝わってくることがあります。これを感じるには、ある程度の経験が必要だとは思いますが、10年もすればその空気感がわかるようになります。これが結構的を射ているのです。
ある先生が若いとき、先輩教師から次のように言われたそうです。
「「七」の力を持っている子には教師である自分が「三」だけ出し、「四」しか持っていない子には、反対にこっちが「六」を出す」2)
それが、子どもの可能性を最大限に引き出す秘訣だと恩師は言うのです。でも、どの子が「七」なのか「三」なのかを見極める確かな基準や根拠はありません。結局はその恩師は自分の経験や勘による「さじ加減」で判断しているわけで、考えようによっては非常に「いいかげん」な話です。でも、その恩師はこう続けました。
「わかるか。いいかげんってのはな、テキトーってことじゃないんだぞ。好(よ)い加減なんだ。」3)
この言葉をもらった先生は、この経験を自著の中で次のように振り返っています。
「コンピュータやアマチュアにはわかるはずのない、経験に培われたこの「いいかげん」の感覚こそが、プロの教員の専門性なのではないだろうか」4)
私は、教育の世界にも「エビデンス」は必要だと思っています。近年では、子どもたちの支援のために、児童生徒の遅刻回数や保健室訪問頻度、忘れ物の頻度など細かな情報をデータベースにして支援に活用する「スクリーニング」の重要性が盛んに言われるようになりました。そうした客観的なデータを有効活用することで、教師による思い込みや決めつけに歯止めをかけ、それまで見えていなかったいじめや虐待の早期発見につながると言われています。そうした客観的なデータは、子どもたちを苦しみから救う一助になるでしょう。ただ、どんなに細かな情報を集めたとしても、それをどう分析し、どういう支援がその子を最も成長させることができるのかは、最終的に教員の判断に委ねられることになります。
教師の「さじ加減」は、両刃の剣です。「いいかげん」になるか「好(よ)い加減」とするかは、豊かな経験とともに、それを共有できる教員同士の十分なコミュニケーション(同僚性)の密度によって決まるのだと思います。それが確保できたとき、「さじ加減」は数値に勝る根拠となるのです。(作品No.216RB)
1)コトバンク「エビデンス」より一部を引用
2)3)4)鈴木大裕(2016)『崩壊するアメリカの公教育』岩波書店、p66