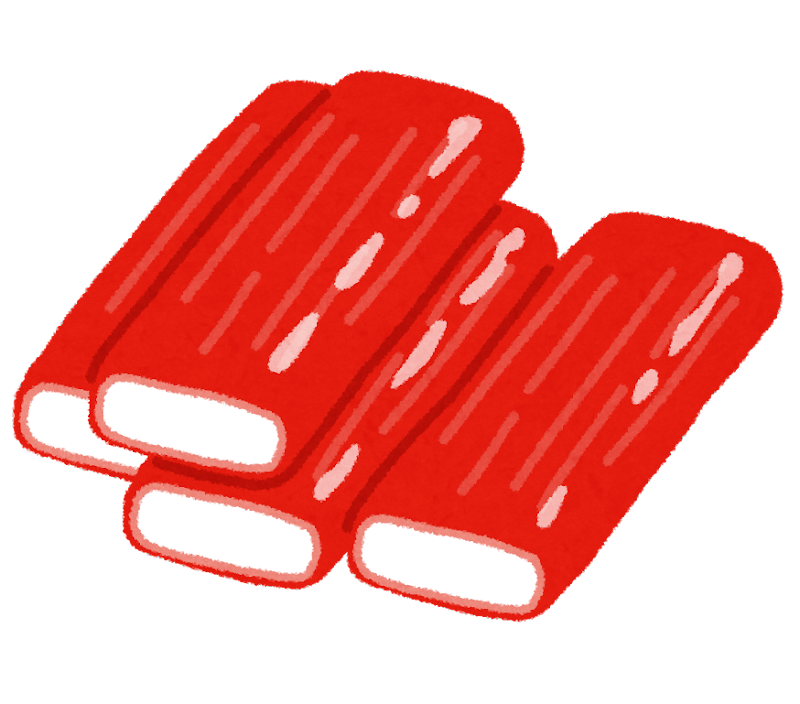新しい年を迎えました。昨年このコラムを読んでくださったすべての方に感謝いたします。教育は国家百年の計とも言われます。私ごときに百年先を考える力はありませんが、今年も私のつたないコラムが少しでも皆さんの力になれたら幸いです。
さて、唐突ですが、昔、中学校の教諭だったころ、こんなことがありました。クラスの女子が職員室の私のところに来て「先生、これもらってください。母がお世話になっている先生にぜひ食べていただきたいと言うので、持ってきました。」
きれいな木箱に入っていたのは、なんと松茸でした。それも、少なくとも20㎝以上はある大物です。一目で高級品であることがわかりました。私は、「こんな高価なものはもらえない」と断りましたが、「このまま持って帰ると母に叱られるから」と彼女が何度もいうので、結局私は受け取りました。(こんな立派な松茸が食べられるという下心もないではなかったのですが)
「一度手に取ってみてください」と言う彼女の言葉に従って松茸を手にしたその瞬間、予想外の軽さにびっくりしました。「そんなはずはない」と驚く私を前にして、手渡した生徒は満面の笑顔を見せています。

そうです。私が手に取った松茸は、大量のティッシュを固めて精巧に作られた「偽物」だったのです。ずしりとくる感覚を予想していた私は、その軽さにすべてを理解しました。そう、私は見事に生徒のドッキリに嵌ってしまったのです。色も形も実によくできていました。彼女が言うには、色付けは水彩絵具ではなくプラモデルなどに使う本格的な塗料を何色も使ったそうで、一部ライターであぶって細工までしたとのこと。そして、渡す場所に職員室を選んだセンスの良さにも感服しました。まさか、職員室でこんなことをするわけがないと普通は思います。それが、彼女のねらいだったのです。
彼女は、声を挙げて笑いながら、この「作品」が、母娘との共同製作であり、完成までに何時間もかかったと話してくれました。私は恥をかかされたというよりも、私を驚かせるためだけにわざわざ時間と手間をかけてくれたことに感激しました。
実はこの話、今後の教育を語るうえで、とても重要なことを含んでいるのです(そのことに気づいたのはそれから10年以上後のことですが)。
私は、最初に偽物の松茸を見たとき「本物だ」と確信していました。「偽物」だと気がついたのは、その後です。だから、初めから松茸はなかったわけです。じゃあ、松茸は本当にどこにもなかったのかというと、実はそうではないのです。私が「偽物」を「本物」だと信じていたときには、私にとっての松茸は確かにあったのです。それが、「偽物」だとわかった時点で、私のなかの「松茸」はティシュの塊に変わりました。でも、一つだけ存在している松茸があるのです。それは、私が「偽物」の松茸を「本物」だと信じていたという事実としての松茸です。その事実は、それが偽物だとわかった後でも覆すことはできないのです。
この覆せない事実は、世の中がどんなに多様化しても、どんなに相対化が進んでもけっして否定することができないのです。私がある時点で感じたことや、何かを信じていたという事実だけは何者であっても否定することはできないのです。
私は、平成7年ごろから現象学的社会学者の祖といわれるシュッツとの出会いをきっかけとして、現象学や社会学に関心を持ってきました。そして、今このような混沌とした教育界を救いうるのは現象学的な視点しかないと確信するようになりました。
学校は今、あるべきものとしての自明の理を失いかけています。30年ほど前にはまだ、「学校(義務教育)は行って当然」という常識があり、それを疑う人は少なかったでしょう。そこには、登校は自明のものだとする世間のまなざしがあったわけです。今はそれもかなり薄らいでいます。社会における様々な場面で多様化と相対化が急激に進んでいるのですから、学校教育だけがそこから逃れるわけにはいきません。
そうした時代だからこそ、現象学的な視点は大きな意味を持ちます。
現象学を一言で説明するのはかなり困難ですが、それでもあえて簡単に言うと、「「これが絶対に正しい」という「真理」をとらえるしくみ」ではなく「物事の意義や価値をたしかめ合う必要が生じた際に、誰もが自分の中で吟味し、共有し合うことのできる「たしかめのしくみ」」1)となります。それまでほとんどの哲学者が求めてきた客観的な「真理」と主観的な認識をどう一致させるかという問題に対して、フッサールは「「そもそも根源とか真理とか求めること自体がもう終わっている」」2)と一刀両断に否定したのです。
つまり、どんな哲学や科学をもってこようとも、目の前にある「もの」が客観的に存在することを証明することはできないというわけです。そんな馬鹿な、と思われるかもしれませんが、次のように考えるとわかってきます。
例えば、冒頭に挙げた松茸が本物であるかどうかを私たちはどうやって判断しているのでしょう。形でしょうか? 色でしょうか? それとも手に取ったときの感触や重さでしょうか? それとも食べてみればわかるだろうというでしょうか?。でも、考えてみてください。現代の技術をもってすれば、松茸とほとんどかわらない味や香りを他のもので再現することは不可能とは言い切れません。
「カニカマ」を考えればさらにわかりやすいでしょう。カニなどまったく入っていなくても色合い、重さ、食感、味、風味のどれをとっても本物のカニと区別がつかない食品に仕上がっています。カニカマは販売開始当時、「本物のカニだ」と信じた人が少なからずいたため、メーカーがわざわざ「風味蒲鉾」という名称に変えたこともあったそうです3)。こう考えてくると、何が本物なのかを確信するのは思ったよりも大変であることがわかります。
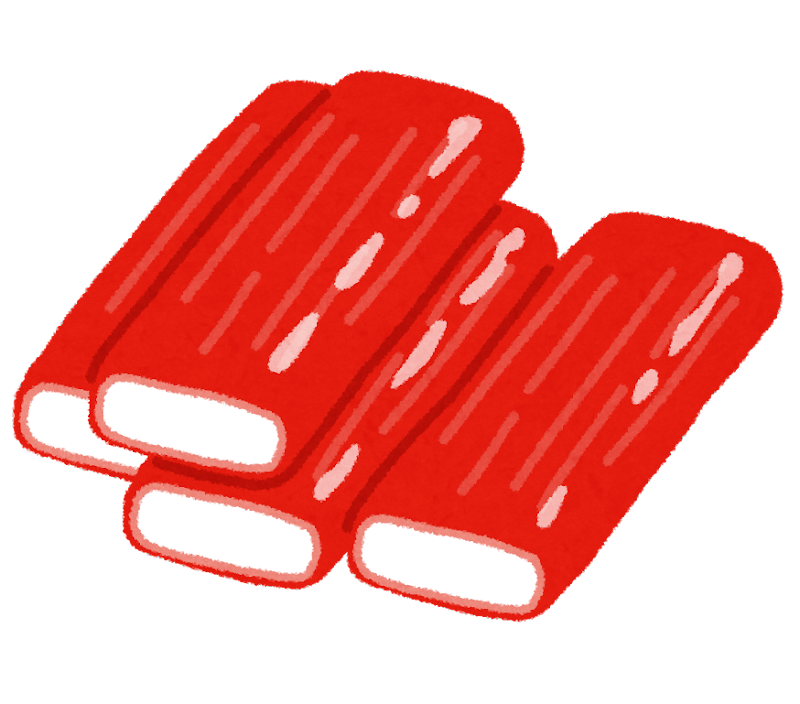
日本の代表的な哲学者である竹田青嗣氏は、こうした人間の判断のしかたについてリンゴをたとえにして次のように述べています。
「たとえば、ここに1個のリンゴがある。普通に考えれば、「『ここにリンゴがある』から私たちは『その赤くてツヤツヤした丸いかたちを目にしている』ことになる。だがこれをあえて次のようにとらえてみる。「『(あの例の)赤くてツヤツヤした丸いものが見えている』から、私は『ここにリンゴがある』と思っている」と。」4」
また、私たちは一度も行ったことがなくてもアメリカという国が存在していることを疑いません。それは、様々な本や人から聞いたこと、インターネットやメディアから受けた情報を信じているからであり、その情報が本当に正しいのかどうかを疑うことがほとんどないからです。でも、それらの情報が本当に正しいかどうかは誰も証明してくれません5)。私たちが信じているから(見えているから)、私たちはそれを当たり前のこととして受け入れているに過ぎないのです。
真実がないとすると、私たちに残された問題解決の唯一の方法は互いの共通了解をいかに得るかということになります。今の状態が本当にいいのかどうかを、まずは一人ひとりが吟味を重ね、その結果を持ち寄って「これがわたしの確信・信憑です。あなたはどうですか?」6)と絶えず対話を続けることで最もよい方法を見つけ出さねばならないのです。
学校が抱える問題の多くが、相対化によって生み出されています。相対化は、教師も保護者も、そして子どもたちをも「寄る辺なき」存在にしてしまいます。これまで述べてきたように唯一絶対の「解」はありません。どこにもない正解をめいめいが正解だとして主張したら収集がつかなくなって当然です。この発想から抜け出せない限り、問題はいつまでも問題であり続けるでしょう。それでも、かつてのように同じ価値を大半の人が共有している状況なら大きな混乱はなかったでしょうが、学校を支える価値そのものが多様化している現代においては、いくら正解の行方を追っても、徒労に終わるでしょう。
そもそも相対化とは絶対的なものを否定する現象のことですから、そこに一つの正解として何らかの方策を押し付けようとしても反発されるのは当然です。それは、学校の理想形というものがどこかにあって、そこに向かうことがあるべき姿だという発想から抜け出せていないからです。そのため両者は、互いに相手を攻撃しようとし、争いやトラブルが絶えなくなるのです。
「これからの学校はどうあるべきか」という問題に対して、お互いが自分の正しさを一方的に相手にぶつけるのではなく、それぞれの見解を持ち寄って実現可能な方向を模索しなければなりません。
(作品No.195RB)
1)、2)、4)竹田青嗣・現象学研究会(2008)『知識ゼロからの哲学入門』幻冬舎、p126
3) https://seafood-reference.com/kanikama/entry1224.html
5)竹田青嗣(1989)『現象学入門』NHKブックス、p210(要約して引用、また文意に影響を与えない程度に加筆)
6)苫野一徳(2022)『学問としての教育学』日本評論社、p63