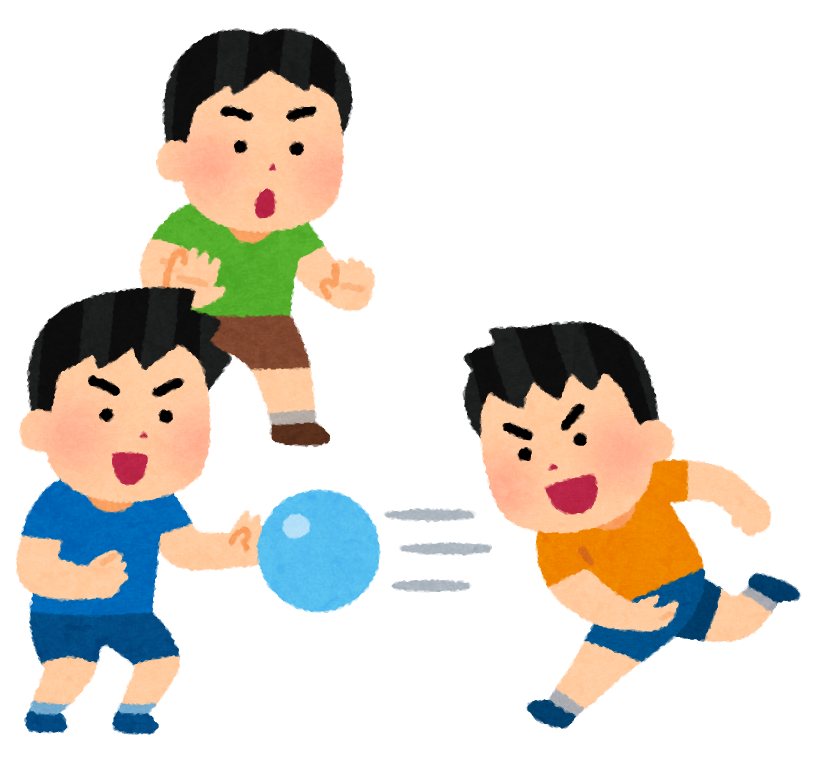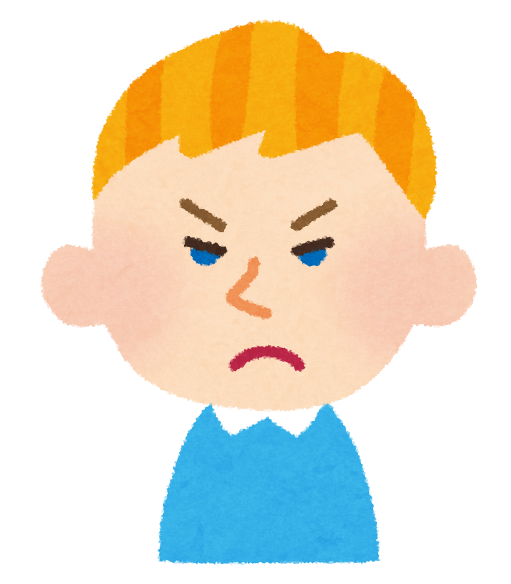これまで、私は主に今の学校を変えようという立場で、このコラムを書いてきました。
私は、「昔はよかった」という言い方があまり好きではないので、学校に関することも、過去の武勇伝のような内容は、極力避けてきました。それは、現職の管理職だった頃から考えてきたことです。
ところが、初めて校長として勤務した小学校で、信頼のおける一人の中堅女性教員から「校長先生の昔こういうことがあったっていう話が結構長いことがある」と言われたことがありました。とても恥ずかしい思いをしました。その先生が私に恥をかかせたという意味ではなく、自分で気をつけているつもりでも、気づかないうちにそういう話をしてしまっていることが恥ずかしかったのです。
指摘されたときは、ちょっとショックでしたが、今思えば、よく言ってくれたと思います。つい調子に乗って話していたことを、私は自分では気づいていなかったわけです。
そもそも「昔はよかった」的な話や「昔はもっとひどかった」的な話に、ほとんど生産性はありません。これからの学校や教員に何のプラスにはなることはありません。それは、単に自己満足にすぎません。だからこそ、十分に気をつけていたつもりなのですが。
ただ、若干の違和感もあるのです。無暗に過去にこだわるのは無駄だと思いますが、自分という人間は、周囲の環境や、自分の行動によって作られているわけですから、あまり自分の経験を軽視し過ぎると、自らが立つ基盤を見失う可能性もあるのではないかとも思うのです。それは、誰かに自慢話をしたいからではなく、曲がりなりにも30年以上教職の身にあったのだから、その経験を振り返って凝縮し、次の世代に引き継げるエキスのようなものを見つける作業も必要なのではないかと思うようになりました。
昔のやり方が今は通じないかもしれないという謙虚さは必要ですが、もっと自分がこれまでやってきたことを整理することも必要だと思うのです。
以前、不易と流行について書きましたが、真の不易というのはなかなか見つけられるものではありません。どんな場でも、どんな人に対しても、あるいはどんな時代にも通じる不易=真実があるとすれば、それはまるでブッダが悟りを開くような深いレベルの話になるのではないかと思います。
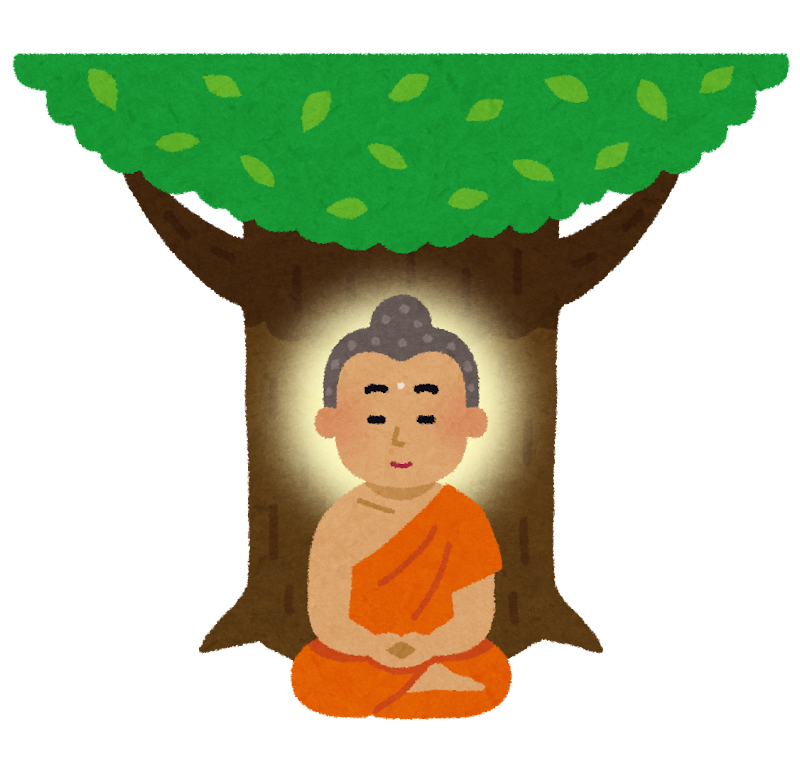
私のような凡人にそんなことはできません。それでも、私には見えなくても本当はどこかに核のようなものがあるのかもしれないと感じることもあります。真実は一つではないと書いてきた私が言うのも変な話ですが、単に私たちには真実の周囲に存在する枝葉や、あるいはまとわりつくような膜のようなものしか見えないだけなのかもしれないのです。
もしそうだとすると、真実は一つではないという現実的な前提を持ちながらも、昔の学校と今の学校に共通する部分はないのかと確認することは必要なのではないかと思うのです。
古いと思ってきた教育の中に実は今に通じる何かがあるかもしれません。
例えば、校内暴力が激しかった頃は、今なら「不適正なかかわり」とされるような指導もたくさん行われていました。時代が変わっても、それが「不適切」であることには違いありませんが、当時はそうしなければ収まらなかった状況もありました。また、暴れる生徒を力づくで抑え込むことは、その生徒を深刻な加害者にしない効果もあったと思います。
私の実感でいえば、当時の多くの教員は生徒との心のつながりを大切にしていました。そして、生徒も体を張ってぶつかってくれる教員を望んでいました。激しく対立しているように見えながら、実は互いに信頼関係を求めていたのです。
今の生徒に同じようにかかわっても何も通じ合うことはありません。それは、今の生徒がぶつかってくれる教員よりも寄り添ってくれる教員を求めているからだと思います。まったくちがったものを求めているようにも見えますが、昔の教員と今の教員に共通して求められるものもあるに違いありません。私は、それは、生徒が今何を求めているかを見ようとする教員の姿勢だと思っています。そのことに関しては昔も今も変わらないでしょう。
今後、学校という制度が大きく変わり、「昔は寄り添うことが大切なんて言っていたなあ」という会話が職員室に生まれるようになるのかもしれません。かつて正しいと思われていた体ごとぶつかるかかわり方が、今通用しないのと同じようになるかもしれません。そのときにはまた、別の共通点を見つける必要があるでしょう。
もしかしたら、そういう積み重ねが、ブッダの悟りのような「不易」に近づく唯一の方法なのかもしれません。
(作品No.194RB)