研修所に勤務していたときに、筑波大学の教授からこんな話を聞きました。その人は外国で欧米の学生と日本の学生を同じゼミで受け持っていた経験があるとのことでした。
「日本の学生に、“小・中学校時代、国語でどんなことを習いましたか?”と聞くと、『ごんぎつね』とか『走れメロス』とか答えます。でも、欧米の学生に聞くと「説明文の書き方」とか「小説の書き方」と答えるのです。つまり、日本の学生は教材名を答え、欧米ではそれが何のための授業だったかを答えるのです。」1)
自分の専門教科が国語だったので、この話には少なからず衝撃を受けました。この教授の言われることが全てだとは思いませんが、私のやってきた授業は内容の理解だけにとどまり、何のためにこの教材を使うのか、なぜ筆者(作者)はこの文(作品)を書いたのか、という視点をもたそうとは考えてもみませんでした。
こうした「何のために」とか「なぜ」といった視点は、メタ認知によって可能になります。
「メタ認知(metacognition)の「メタ(meta-)」とは,「高次な」や「一段上の」という意味を持つ接頭語で,「認知(cognition)」は,見たり,聞いたり,考えたりなどといった知的営みや活動を指す言葉です。つまり,メタ認知とは自らの認知活動を高次な(一段上の)レベルから認知することを意味する言葉になります。」1)
つまり、今自分がやっていることがどういう意味を持っているのかを「一段上の」視点によって理解しようとすることです。冒頭の欧米の学生が「説明文の書き方」と答えることができたのは、このメタ認知によって、教材の理解を越えた「授業の意味」を十分に理解していたからでしょう。
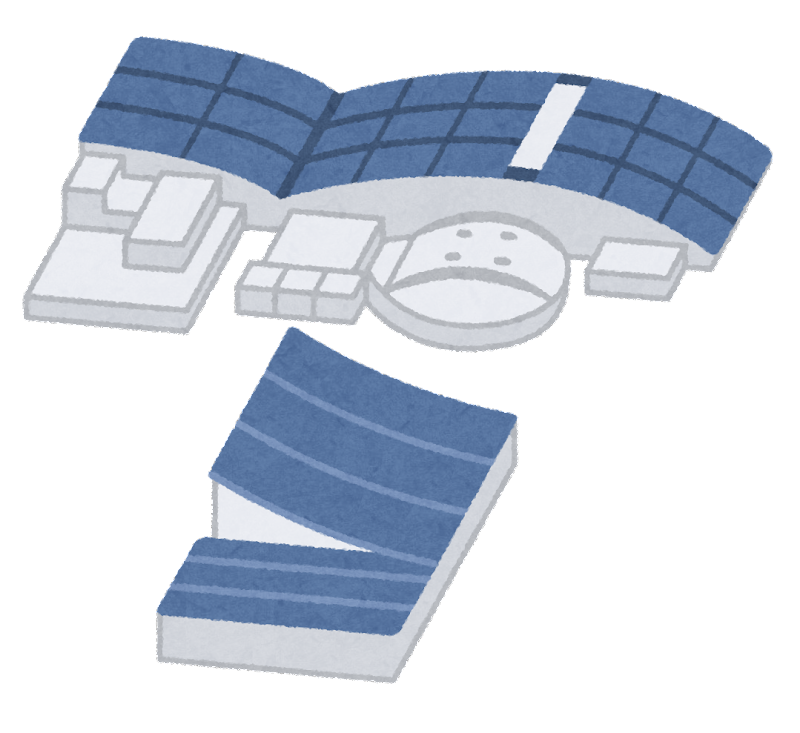
メタ認知は日本語の「俯瞰」に近いものだと思います。例えば、校舎の全体像を写すために航空写真を使うのとよく似ています。また、車のカーナビを想像してもいいかと思います。ナビは人工衛星(GPS衛星など)を使って、高いところからその場所を広角で捉えることができます。角度が小さければ、正確な道案内はできないでしょう。
国語の説明文の授業に即して言えば、教材の内容を正確に理解した上で、その文がどんな構成になっているのか、何のためにこの段落でこの具体例を用いられたのか、そして筆者はなぜこのような文章を書こうと思ったのかなどを考える視点をもつということです。そうした読みをするためには、教材の全体を見渡す必要があります。全体を見渡すことで、筆者の意図が見えてきます。自分が筆者になったつもりで読むと言ってもいいでしょう。筆者は、必ず意図をもって文章を構成しているはずです。文中には書かれていない「高次な」意図を汲み取ることは、自分が説明文を書こうと思ったときに必ず生かされます。
私が小学生のころ、よく、説明文の授業で、形式段落ごとの要点まとめる作業をしていました。丁寧に読むことは大切ですが、あまり細かくやり過ぎると生徒の視点が近視眼的になり、全体像が見えにくくなります。そういうときには、視点を読者から筆者に変えることで、文章全体を見ることが可能になります。
以前注目された「PISA型読解力」も、メタ認知を基調としています。これも児童生徒の全体を見る目を養い、何のために今この授業をしているのかを考える機会を与えることを重視したものです。この考えは、現行の学習指導要領でも生かされています。
このメタ認知は、私たちが仕事を進める上でも重要な視点です。今目の前でやっていることが子どもたちのどんな部分を育てることにつながるのかをちょっと意識するだけで、児童生徒への声のかけ方も変わってくると思います。
また、自分よりも少し経験のある人になったつもりで(授業で筆者の視点をもつのと同じように)その人を見てみることも大切です。学級担任なら学年担当を、学年担当なら教務の先生を、教務の人なら教頭先生を、教頭先生なら校長先生を、といった具合にです。自分のことに精一杯だという人も、時々でいいので試してみて下さい。きっとそこには新しい発見があるはずです。「自分ならどうするだろう」と考えるだけで自分の視野を広げることができます。その姿勢は、将来その立場に立ったときに生かされるだけでなく、自分の仕事や学年のことを「俯瞰」する視野や思考につながっていきます。
(作品No.42HAB)
- 「岩手大学教育学部准教授 久坂哲也「メタ認知と学び」(ベネッセ教育総合研究所 マナビコラム https://berd.benesse.jp/special/manabucolumn/classmake19.php)









