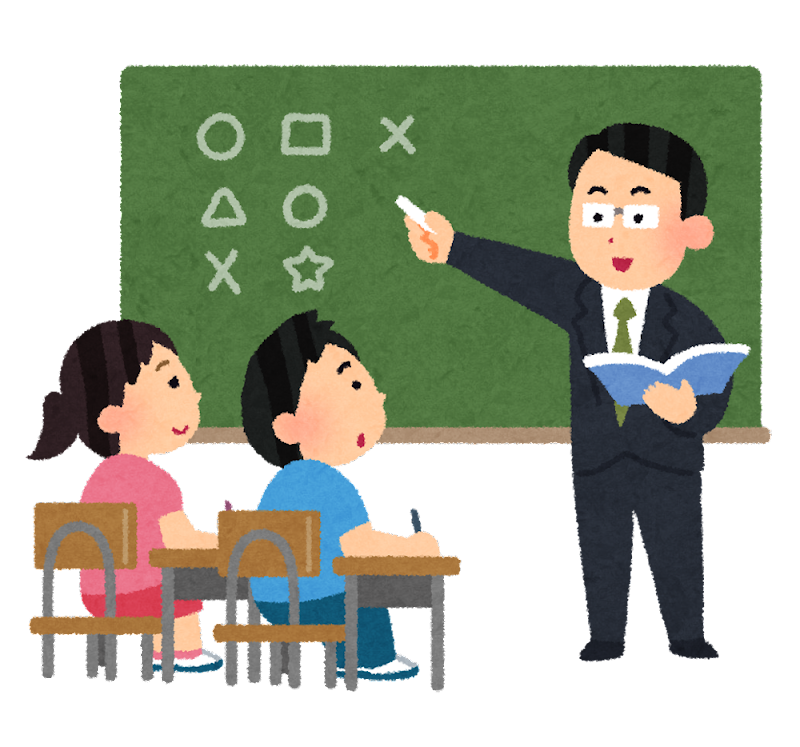書店に行けば名言集の類いの本は山ほどあります。ネットを検索したらもっと膨大な数の名言が検索できます。話のネタや通信のネタに使えるものがあればと思ってよく利用しますし、本もそこそこ買いました。でも、いわゆる「名言集」というのは、意外と使いにくいものです。例えば、100の名言が掲載されている本で「これはいい」と思えるのは数個あれば良い方です。中には「買うんじゃなかった」というものもあります。最近では、この手の本を買うときには、ぱらぱらと頁をめくって一つでも「これは」と思うものがあるかどうかを確認するようにしています。一冊に一つでも「これはいい」と思える言葉があれば買った価値はあると思うからです。自分にとってしっくりくる言葉でないと人には言えないし、自分がなるほどと思わないのに人に伝えることはできません。

私にとって最も効果的なのは、自分の記憶の中で「そういえばあんなこと言っている人がいたなあ」というおぼろげな記憶からキーワードを探し、ネット検索して具体的な人名や正確な言葉、出版元等を調べるというやり方です。そうやって選んだ言葉は、結構しっくりきます。
ネットは膨大な量の情報で溢れています。暇つぶしに見るときは良いですが、そうでないときは、目的を持っていないと情報の波の中で溺れそうになります。当たり前のことですが、私の中で長い間記憶に残っているということは、それだけ、自分にとって意味のある言葉だということです。名言集のコピペは所詮借り物でしかないわけです。
それでも時には、名言集やネットの中にも「これはいい」という言葉を見つけることがあります。でもよく考えると、その言葉はもともあった自分の考え方を後押ししてくれるものだったり、記憶に残った言葉と結びつけられたりするものです。結局、自分の記憶や経験(読書を含む)、または考え方と結びついて納得できる言葉だからしっくりくるんだと思います。しっくりきていないのに伝えるのはなんだか嘘をついているようで気持ち悪い。(と言いながら、何となくネットを見ているときに、「あっ、そういえば」と気づくこともありますから、なんとなく見ることがまったく無駄かというと、そうとは言い切れないですが。)
そして、全く自分の考えと違う言葉に出会ったときは、逆にその中身をできるだけ詳しく確認したくなります。もしかしたら、真逆の考えが新しい発見(経験)を生み出してくれるかもしれないと思うから。(作品No.22HB)