退職して一か月ほど、まったくの無職の期間がありました。収入はなくなりましたが、時間だけは有り余るほどありました。最初のうちは、自分のしたいことを好きなだけできる喜びで満ち溢れていました。私の場合、辞めたらブログを立ち上げたいと思っていたので、その手続きやブログに載せる文章を書くことで、一日があっという間に過ぎていきました。
でも、しばらくすると自分一人で活動することになんとなく違和感を覚えるようになりました。毎日、楽しいのですが、自分だけでやっていることには、どんな意味があるのだろうという葛藤のようなものが生まれたのです。
別に何かの試験に合格しなければならないわけでもないし、上司に課せられた仕事があるわけでもないのですから、自分が楽しければそれでいいと言えばいいのですが、それでも、何となく落ち着かないのです。それは、ある種の罪悪感に近いものでした。
しかも、その罪悪感は自分に向けられた罪悪感とは少し違うのです。何か、人としてもっと根源的なもののような気がするのです。大げさかもしれませんが、それは生命体として生まれ落ちた時からもっている「何か」であるように感じたのです。説明できない直感のようなもので、怠惰を否定する社会の規範から生まれるような表層的なものではなく、何かにせっつかれるような気分なのです。
そして、最近思い始めたのが、こうした私の感覚は、ひょっとしたら不登校の児童生徒の心情にも同じようなものがあるんじゃないだろうかということです。彼らの精神状態は、私のようにのんびりと過ごす老人の気分とは、その深刻さにおいてまったくレベルが違うものだとは思いますが、それでも共通点はあるように思うのです。
周知のとおり、不登校は年々増え続けています。実数はもちろんですが、これだけ少子化が進んでいることを考えれば、その増え方は尋常ではありません。今や中学校ではクラスの中で5~6人はいる計算になるといいます。
ただ、逆の見方をすれば、他の34~35人は登校できているのです。それが、不登校の子にとってみれば、非常につらいことなのです。なぜなら、大半の子が当たり前にできていることが自分にはなぜできないのかという罪悪感がそこに生まれるからです。
不登校の子どもにとって、世間は非常に気になる存在です。いくら「あなたはあなたのままでいいんですよ」と言われても、納得できません。むしろ、そんなことを言われたら「見放された」と感じてしまうでしょう。つまり、自分以外の「声」が頭の中で大きな声を上げて自分を否定していると感じてしまっているのです。自分の中にある「世間」が、自分を「何をやっているんだ」「もっとしっかりしろよ」とせっついてくる。それが、彼らの感じる最も重い重圧となるのです。
私の抱いた感覚も、レベルこそ違え、自分の外側から「お前のやっていることは、本当に自分の人生にとって有益なことなのか」という「せっつき」の声が、つかみどころのない罪悪感を生み出しているのです。共通するものがあると感じたのは、どちらも「せっつかれる」感覚があるからです。ただ、私の場合はたとえ「せっつかれて」もその先にあるものは、自分のやりたいことをどうするかという希望へとつながるものです。それに対して不登校の子への「せっつき」は、自分を完全に否定されていると感じる「せっつき」です。そこが大きく違うところです。
最近、不登校について書かれた本をいろいろと読みながら願うことは、自分の外から聞こえてくる「声」も、いつか必ず自分の中に蓄積されていくエネルギーによって、少しずつ小さなものになっていき、いずれはそれが自分の生きる指針となるということに気づいてほしいということです。
その気づきを得るのは、子どもだけではなかなか難しいでしょう。学校に「普通」に通っている子が、何も自分よりも偉いわけではない、同じ価値を持った人間なのだと思える環境を大人はつくっていくべきです。
今、学校は、多くのことを背負いすぎています。それが、教員の疲弊につながっています。しかし、問題はそれだけではないのです。学校が、たとえ善意であったとしても、過剰に多くのものを抱え込んでしまったが故に、学校から外れたときに、自分には何も残らないのではないかと子どもは錯覚してしまうのです。
学校の相対化は必ずしも歓迎できるとは思いませんが、それでも、胸を張って既成の学校以外を選択できる社会の空気みたいなものが必要です。それには、ホームスクールも含めて、フリースクールなども、その学習内容に応じて学校として認めていかなければ、不登校の子どもの苦しみは消えません。国も「不登校特例校」(このネーミングもセンスがないと思いますが)を設置していますが、選択肢として市民権を得るには、まだ数が少なすぎます。
また、既成の学校が選択肢の一つになることに拒否反応を示す教員は多いと思います。でも、苦しんでいる子どもを放置してまで、今の学校だけを学校とすることにどれだけの意味があるのかと思います。
子どもたちに、多くの、そして「正規」の選択肢を与えることができれば(社会的に用意できていれば)、最初の学校に合わなかったとしても、しばらく休憩すれば身近にある別の学校に手を伸ばすことができます。それは、自分の罪悪感を消すための行為ではなく、積極的に「生」を求める行動としての選択になると思うのです。
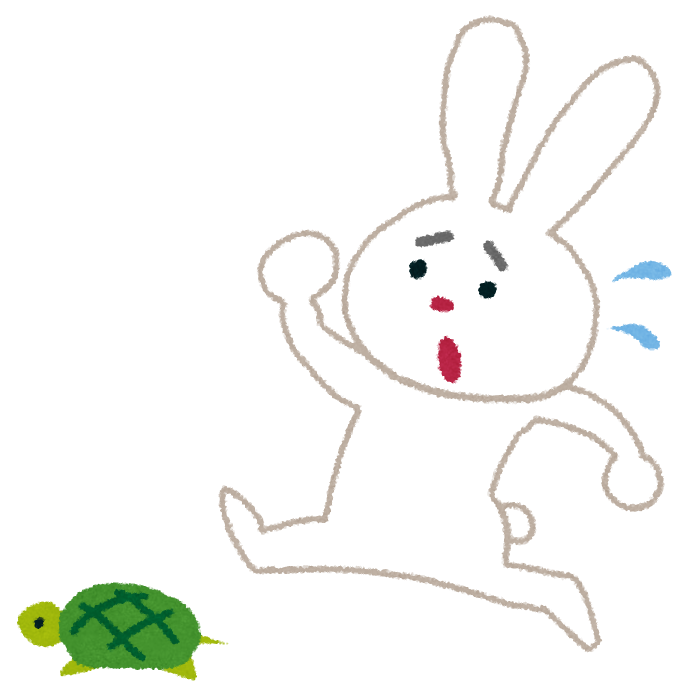
とはいえ、私は、いわゆる新自由主義者が訴える(すでに実施されている)学校選択制には賛成できません。それは、必ずしも苦しんでいる子どもを救うために有益であるとは思えないからです。この制度には、学校を競争原理によって学校の質を向上させようとする意図が透けて見えます。競争は必ず結果を求めます。誰の目にも明らかな数値としての結果を学校に求める危うさが伴います。
不登校の子どもは、競争原理に決して馴染むことはないでしょう。比較や競争に耐えられないからこそ学校に足が向かないのです。
そこには、彼らを追い込んでいる「声」が大音量となって響いている気がしてならないのです。
(作品No.182RB)
