今、学校が抱えているさまざまな問題は学校というシステムが制度疲労を起こしているところから生じていると思います。中でも公立学校における学級制度は明らかです。学校の基本単位として「あって当たり前」のものとして学校の中核に位置する学級ですが、多くの矛盾を抱え、深刻な問題を発生させているのに改革の手が入らず、そのことにとってさらに矛盾が大きくなっています。こうした学級はその存在を疑われることもなく、自明のものとされ、すべての公立学校で学級を編成することを前提とした教育活動が展開されています。
学級の法的根拠は実に曖昧です。学級とは何かという規定や定義はいったいどこに示されているのでしょうか。例えば、学級の編成等について定めた「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(いわゆる「標準法」)の第三条(学級編制の標準)では「公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする」とされていますが、ここに示されているのは学級の構成員に関する規定であり、学級そのものの規定でもなければ定義でもありません。「学校には学級を設置すること」といった文言はありません。また、学校を新たに作るときの基準となる「学校設置基準」にも同様の文言が書かれているだけです。新たに学校を設置する場合の基準(当然現存の学校が学校足りえる基準でもありますが)に、学級編成を義務づける文言がないのですから、素直(?)に読めば、学級編成を行わず単位制にすることも可能であることになります。当然、児童生徒の学習内容を規定する学習指導要領にも明記されてはいません。私の知る限りでは、現在の形の学級を法的に規定するものは、明治24年(1891年)に出された「学級編制等ニ関スル規則」しかありません。以下、その内容です。
(学級とは)「一人ノ本科正教員ノ一教室ニ於イテ同時ニ教授スヘキ一団の児童ヲ指シタルモノニシテ従前ノ一年級二年級等ノ如キ等級ヲ云フにアラス」
この「規則」が今も効力を持っているのかどうか判然としないのですが、今から約130年前の規則が今も生きているとしたら制度疲労を起こして当然です。
このように、法的な根拠が曖昧であるにも関わらず学級の構成員である児童生徒は、同年齢であるというだけで同じ学年とされ、自らの意志とは関係なく強制的に学級に振り分けられます。その上、よほどのことがない限り年度途中での学級変更も現実的には認められません。ここまで閉鎖的な空間というのは、現代の日本社会において他に類を見ないでしょう。個人の自由や選択の自由がこれほど保障されている日本の社会の中で、強制的に所属する集団を決めるのであれば、それ相応の理由や効果が法的レベルで示されないといけないはずです。しかし、学級の教育的効果については文科省の通知レベルでしか示されていません。にもかかわらず、学校に作成が義務づけられている指導要録には各学年における学級担任を記載する欄が設けてあり、学習指導要領や生徒指導提要も、学級編成を自明の前提としてその経営をどのようにすることが望ましいかが示されています。
私が、学級の法的根拠にこだわるのは。学級の閉鎖性によってじつにさまざまな問題が発生している現状があり、それらの問題が年々深刻なものとなっていると感じるからです。こうした指摘は私だけでなく、長年にわたって多くの専門家によって指摘されてきました。
超がつくほどの閉鎖空間では、いじめが発生しやすいこと、一旦発生したいじめが長期化しやすいこと、閉鎖空間に対する拒否反応によって登校できなった子どもたちが増えていること、あるいは学級担任による強引な学級経営によって(いわゆる学級王国)自主性が著しく阻害される危険性があること、自分で考えようとしない子どもが増えていることなどあげればきりがありません。それでも、学級は形を変えることなく100年以上も続いてきたのです。
ここ何年かで、公立中学校の大幅な改革を行ったいわゆるカリスマ校長の話がいくつか話題となりました。定期考査を廃止したり、校則を完全に撤廃したり、教員が一切叱らない方針を打ち出した校長もいます。また、最近では個々の生徒が自ら学習のめあてを考え自ら振り返りを行う「自由進度学習」(蓑手章吾『自由進度学習のはじめかた』学陽書房、2022年、初版は2021年)という実践(小学校)も報告されています。これなどは、かなり学級を柔軟に考えた素晴らしい実践だと思います。これまでの学級は、学級を単位とした一斉授業にこだわったがために、膨大な数の「落ちこぼれ」(落ちこぼし?)を生み出してしまいました。それに比べて「自由進度学習」は、個別に目標が違うわけですから他の子と比べられることはありません。また、めあては自分がぎりぎり超えることのできないレベルに設定するよう助言しているため、6年生でも2年生の算数に取り組む児童もいるそうです。このシステムは「きのうの自分を越える」ことを意識させることになり、子どもたちは成長する実感が持ちやすくなります。
これらの実践は、積極的に「今できる範囲で最大限のことをしよう」としたものであり、学級の閉鎖性を緩和する意味でも大きな前進であると思います。けれども、そうした優れた実践においてさえ、学級という枠組みは残されています。学級そのものを根本的に見直したわけではありません。
そもそも、明治24年に修得制の「等級制」を履修制の「学級制」に変更したのは、上級クラスに進級できない子どもの多くが退学してしまうという事態が生じたからだといわれています。また、「教育目標の変化、すなわち個々人の知育を中心に教育を行うことから、訓育、とりわけ日本国民としての一体性を涵養するための道徳教育を中心とするようになったことが、大きな理由とされている」(濱名陽子1983「わが国における『学級制』の成立と学級の変化に関する研究」、柳治男(2005)『<学級>の歴史学』講談社選書メチエ、p143より重引)という指摘の通り、国の方向転換という意味もあったようです。ただ、いずれにしても学制発布から20年弱で最初の制度疲労が起こったわけです。制度疲労を「制度や法律が運用されているうちに社会状況が変わり、実情とかみ合わずにうまく機能しなくなること」(コトバンク)とするならば、国が求めていた姿(近代化の推進)からの乖離が激しくなり、制度そのものの維持が困難になったために、思い切った制度改革をしたということです。時代背景は今と全く違いますが、「だめだ」と思ったときに素早く対応したという点においては評価できると思います。逆に言えば、ここまで社会とのずれが大きくなった現代の学校のシステムを放置していることは、国の怠慢であると言っても過言ではないと思います。
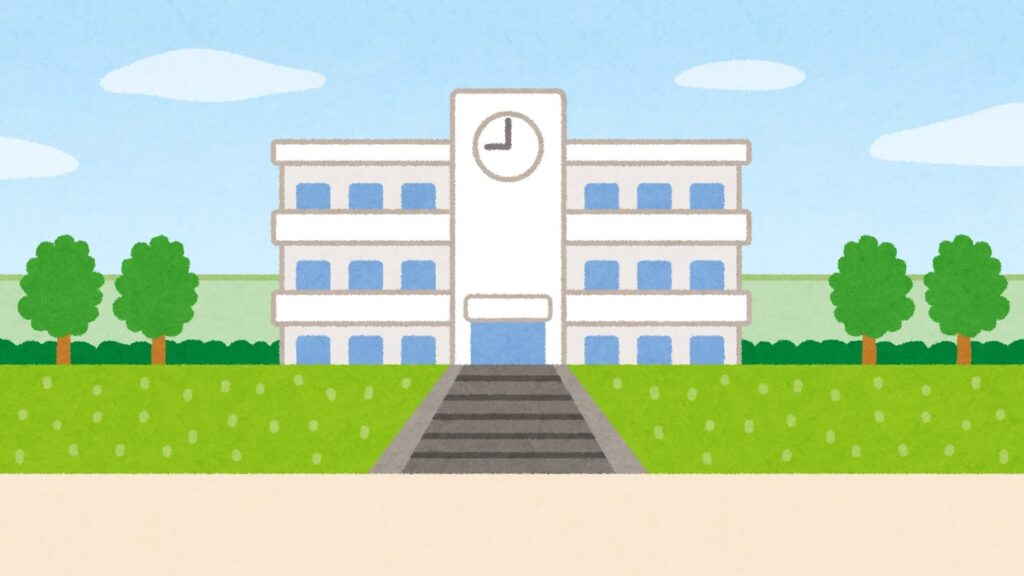
何が深刻な問題なのか、それは不登校という現象一つとっても明らかです。不登校の児童生徒は年々増え続けています。それを、個人の資質の問題であると片づけることはできません。数十年前なら、アメリカの「学校恐怖症」の流れで心理的な問題として見ることもできたかもしれませんが、今や不登校が「心の病」が原因の大半を占めていると信じている人はほとんどいないでしょう。不登校は明らかに社会的な現象であり、その現象は社会全体に広がった私事化による学校の相対化が根本的な原因であると私は思っています。確かに今でも神経症的な症状によって学校に登校できない子どもはいるでしょうが、それが生まれ持った特性が原因であるという例は相対的に少なくなっていると思います。
先述したように明治期に学級制に切り替えたときも、生徒の学校離れが引き金になっていました。それは相対化とは言えないでしょうが、生徒が学校から離れていくという意味では同じ現象です。「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(令和3年10月13日(水)文部科学省初等中等教育局児童生徒課)によれば、中学校の不登校生徒は166,241人(平成28年度108,999人)に達し、中学生全体の5.6%(平成28年度3.25%)に及んでいます。平成28年度の同調査結果と比較すれば、その増加が著しいことは一目瞭然です。子どもの数が減っている中で不登校の数がこれだけ増えているのは、まさに緊急事態であると言わざるを得ません。この事態を生徒個人の資質に求めたり、教員の対応にのみ求めたりしても決して解決しないでしょう。明治期と同様、生徒が学校から離れていく今の事態を根本的に解決するには、学級という組織を自明のものと考えない改革が必要です。
私は今すぐに学級を解体することを主張したいのではありません。あまりに急速な改革を進めれば、学校現場に無駄な混乱を引き起こすにちがいありません。けれども、多くの苦しんでいる子どもたちを救うには、少しずつ学級の閉鎖性を緩やかに変えていく努力を国が先導して行うべきだと思うのです。
(作品No.174RB)
