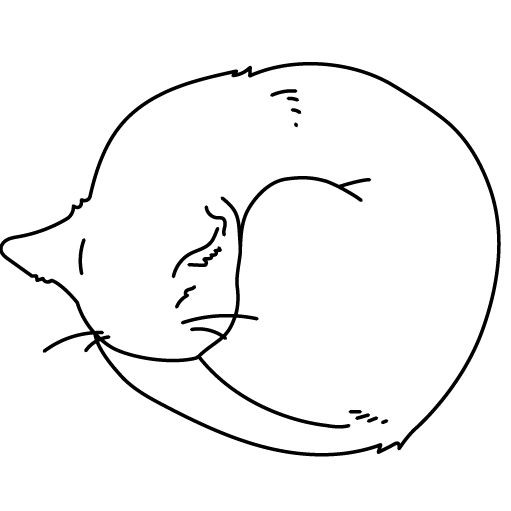昨年(令和3年)の3月29日、公立中学校の校長であった私は、突然の胸痛に襲われ校長室で倒れました。意識はあったものの、その苦しさと不安のためにその場にうずくまってしまいました。校務分掌(学校内の人事)が佳境を迎えていた時期。朝の8時ごろのことです。「こんな大切なときに校長の私が職場を離れるわけにはいかない」。そう思って、駆けつけてくれた救急隊員の方に、ひたすら「大丈夫です。もう収まりました」と何度も繰り返しました。しかし、本当のところは突然起きた自らの体の異変に恐れ、震えていました。もしかしたらこのまま・・・とまで思いました。春休み中ではありましたが、部活動のために登校している生徒も少なからずいました。私を乗せたストレッチャーは、そうした生徒たちのいる下足場の真横を通って救急車に向かいました。その間、かすかに生徒の驚きの声がいくつか耳に届きました。「ああ、これでもう学校には戻れないだろう」という思いがぼんやりと浮かんでいました。
搬送された病院でカテーテル検査を受け、心臓につながる大切な三本の血管がどれも半分くらいに狭くなっている(血管狭窄)と医師に告げられました。ただ、医師の診断は「すぐに手術や治療が必要な状態ではない」とのことでした。私はその言葉を聞いて、逆に全身から力が抜けていくのを感じ、自分の体が思うように動かせなくなりました。私は、極度のストレスによって疲れ果てていたのです。私は、絞り出すような声で同席してくれていた娘を診察室から出るように言い、医師に苦しさを訴えました。医師は一向に医師の顔を見ようとしない私の様子にただならぬものを感じ、すべてを察してくれました。そして「よく話してくれましたね。その一歩がなかなか踏み出せない人が多いんですよ」と受け入れてくれ、院内常駐のカウンセラーを紹介してくれました。
院内の相談室に移動する際、私はカウンセラーにつかまっていないとまともに歩けない状態でした。カウンセラーの人は、40代くらいの女性で、非常に柔らかく包み込むように私から話を聞き出してくれました。苦しそうに話す私のペースに終始合わせてくれました。途中で言葉にするのがつらくなったときも、何も言わず、黙って次の言葉を待ってくれました。途中で口をはさむことは一切ありませんでした。「寄り添う」というのはこういうことなんだと、しみじみ思ました。そして、ようやく家族以外に自分の話を客観的に聞いてくれる人に出会えたと感じました。私は、自分の情けなさや、職場に自分なんていない方がいいんじゃないかという思い、先ほどのカテーテル検査の結果に異常が出たほうが気が楽だったこと、現実の世界に実感がもてないことがあること、数ヶ月前から午前中は気分が重くて仕事にならなかったことなどを、少しずつ話すことができました。
カウンセラーの女性は、私が「こんな状態の私なんかいない方が学校はうまくいく」という意味で「私は学校にいないほうがいい」と言ったのを「この人は自殺するかもしれない」と感じたのだと思います。驚くべき速さで次の病院につないでくれました。最初に搬送された病院には1日だけの入院となり、翌朝10時には退院、11時には次の病院の予約がとられていました。
次の病院は「精神科」でした。心療内科ではなく本格的な精神科の病院です。予想はしていたとはいえ、やはり自分の状態はそこまで悪いんだと自覚せざるを得ませんでした。病院に向かう車中、運転する家内に入院も辞さないことを告げました。とにかく、まったく気力がわいてこず、このまま学校に戻っても何の役にも立たないのは明らかだと思ったからです。残っていた校務分掌の決定が困難を極めているだろうということ、年度当初の始業式や入学式が校長不在となること、また、それらのことで職員や保護者からどんな反応があるのだろうという不安が頭をよぎりましたが、それでも「もう無理だ」と思いました。そして、その瞬間、退職を決意しました。

入院にあたって、スマホやたばこ、ライターを病院に預けるように言われ、他にカッターナイフやはさみなどを持っていないかを確認された後、自分の病室に案内されました。
病室のあるフロアは鉄の扉で常時施錠されていました。中に入ると案内してくれた看護師の方がすぐにその扉に鍵をかけました。そのときの「ガチャ」という音が今も耳に残っています。私は、その音によってはじめて自分の現実を知らされたような気がしました。「ああ、ここまできたのか」と。いや、もっと正直に言えば「ここまで落ちたか」と感じたのです。私は教職に就いてから30年以上、目の前の生徒に対して偏見と差別の愚かさを説いてきたはずなのに、実のところはその自分自身がこの病気に対して明らかに偏見を持っていたのです。だからこそ、そのときの自分の状態を「情けない」と感じ「落ちぶれた」と思ってしまったのです。
その後一か月の入院を経て、2か月間自宅で療養し、学校現場に復帰しました。先にも書いたように、入院を決めた時点で「辞めよう」と思い、市の教育委員会にもその旨を伝えていました。私が辞めない限り次の校長は決められません。正式に辞めれば、年度途中であっても市か県のいずれかから指導主事などが校長に赴任することもできる、そう考えました。しかし、県教委に勤務していたときに、県内のある学校で教頭が急逝し突然課内の筆頭(課長の次席で課内の事務や調整をするリーダー)が引き抜かれ、課のメンバーがどれほど混乱したかを思い出しました。そう考えると、やはり年度途中での退職はあまりに無責任すぎると思い直し、市教委の温かい支援や励ましもあって、とにかく年度末までは続けようと思い直しました。
全国にどれほどの中学校があるのかよく知りませんが、数多ある中学校の中でこの病気(適応障害)で精神病棟に入院した校長はほとんどいないと思います。ある意味で最悪の校長なのかもしれません。でも、この経験によって私は「寄り添う」ことの大切さを身に染みて感じました。先述のカウンセラーの方はもとより、療養中は家族がとにかく温かく寄り添ってくれました。市教委も同じです。
そして、自分にしかできない何かがあるはずだと考えた末、始めたのが教職員向けの「校長コラム」でした。生徒に寄り添うとはどういうことなのか、今までのやり方や生徒への接し方は本当に変えなくていいのか、もっと広い視野をもつべきではないかというようなことを、できるだけ柔らかい表現で示そうと考えたのです。
生徒を真に「見ようとする」意識と「変わる」勇気
学校には、学校独特の文化や価値観があります。それは一貫性のある教育を進める上では、ある程度必要なことです。けれども、今まで疑問に思うことなく(あるいは、それが生徒のためになると信じて)やってきたことのすべてが、今、目の前にいる生徒にとって有益だとは限りません。例えば、今までよく言われてきた、「押さえを利かす」指導では、生徒は心を開いてくれなくなっています。
価値観の多様化は加速度を増し、変化の激しい社会の中にあっては、何が正しくて何が間違っているのかを見極めることさえ難しい時代になってきました。私たちは、今、目の前の生徒に何が起こっているのか、何に悩んでいるのか、そして、学校にどんな意味づけをしているのか、それら一つ一つにしっかりと目を向け一人一人に寄り添う姿勢がなければ、いずれ私たちは生徒から見放されてしまうときがくるのではないかと思うのです。とても都会とは言い難い私の勤務していた地域ですら、私立中学への進学を選択する児童が増え続けています。寄り添う「指導」は、今始めないと間に合わないかもしれません。それには今までの何倍もの時間がかかるでしょう。それでも子どもたちの見ている現実は、日々変化しています。その変化に遅れをとらないためにも、これまでの「指導」に固執することなく、子どもに徹底的に寄り添うことが必要です。近年盛んに言われている「働き方改革」は、その時間を確保するためにこそ必要なのです。私がかのカウンセラーにしてもらったように、生徒の話を、生徒のペースでゆっくりと聞く時間を確保することが急務です。
そして、それ以上に重要なのは、現実をありのままに見ようとする意識だと思います。人は関心のないものに対しては、すぐ目の前にあっても気づかないものです。子どもをありのままに見ようとする意識、それこそが「子どもを真ん中に置く」ということだと私は思います。教師が変わる勇気を持たなければ、子どもはどんどん私たちから離れていくでしょう。
最近の子どもたちは「ひ弱」になったという人がいます。「些細なことで傷つき親に助けを求める。ちょっと強く叱ると学校に行きたくないと言い出す」と。その真偽を客観的に証明することはできません。でも、それが仮に本当だとしても、私たちは子どもたちを「ひ弱」だと決めつけておしまいにすることはできません。昔の子はたくましかったと何万回嘆いたところで何の意味もないのです。真面目な先生ほど自らが受けてきた教育のあり方に基づいて、あるいは先輩諸氏の武勇伝に魅力を感じ、「教育の真実は一つだ」として自らが正しいと思う方向に子どもたちを引き上げようとします。それがすべて悪いとは思いません。信念を持って子どもに対することも必要でしょう。でも本当に大切なのは、目の前の子どもが「ひ弱」に見えたとき、なぜそう見えるのかを考えることだと思います。その答えは教師の側にはありません。子どもたちに寄り添って子どもたちに教えてもらうしかないのです。子どもたちは、寄り添ってくれない教師からは距離をとるようになります。そうなればなるほど、目の前の子どもたちの「現実」(見ているものとそこに込められた意味付け)は見えなくなり、教師の目に映る子どもたちと子どもたちが見ている現実とのギャップは大きくなります。そのギャップが真面目な教師をしらずしらずのうちに苦しめ始めています。過去の歴史を振り返ればわかるように、教育の真実は時代によって振り子のように揺れ続けるものです。「変化を続けるからこそ変わらないでいられる」(ニール・ヤング)という言葉どおり、「変わり続けることが唯一の真実だ」と考え、ありのままの子どもたちの姿から学ぼうという姿勢が必要なのだと思います。
わかったような偉そうな書き方になってしまいました。また、最初ということで肩に力が入りすぎた文章になってしまいました。次からは、もう少し短めにやんわりと書いていきたいと思います。そして、周囲から認められず悶々とした日々を重ねている子どもたちに、変化の激しい学校の中にあって奮闘する先生方に、少しでも何かが伝わればと願って、このブログを始めました。 (作品No-95B)